【BtoBの革命前夜?】SaaSのプロたちが熱狂、『TAAAN』のすごすぎるネットワーク効果を徹底解剖──KAENが仕掛ける“イノベーション流通革命”とは
Sponsored「良いプロダクトが、必ずしも売れるわけではない」。
これは、日本のSaaS業界に身を置く者であれば、誰もが一度は直面する厳しい現実である。優れた技術、革新的なアイデア、そして社会を変えるという熱い情熱を胸にプロダクトを磨き上げても、それを本当に必要とする顧客へと届ける「流通」という名の壁に阻まれ、志半ばで失速していくスタートアップは後を絶たない。
多くのビジネスパーソンは、その原因を「営業力不足」や「マーケティング戦略の欠如」といった、個社の努力不足に帰結させてしまうかもしれない。しかし、もしその根源が、SaaSというビジネスモデルそのものではなく、それを届けるための「流通」の構造的な欠陥にあるとしたら──?
本稿では、この構造的な課題に正面から挑む一社の挑戦を追う。株式会社KAEN(以下、KAEN)。彼らは、単なるセールステックツールを提供するのではない。優れたプロダクトを持つ「創り手」と、高い専門性を持つ「新世代の販売パートナー」とを、彼らの中核事業『TAAAN』というマーケットプレイスで結びつけ、テクノロジーと人間の介在価値をかけ合わせた“ハイブリッドな流通革命”を仕掛けている。その証明として、プラットフォームの流通総額(GMV)は直近2~3年の間、年平均2倍以上の目覚ましい成長を遂げている。
彼らがいかにして、この難解な課題を解き明かそうとしているのか。その事業の核心を徹底的に解剖し、日本のビジネスシーンに新たな可能性を示したい。
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
- EDIT BY TAKASHI OKUBO
「流通の断絶」──なぜ、良いSaaSは“届かなかった”のか
なぜ、SaaSが、期待されたほど日本の生産性を向上させられていないのか。 SaaS市場の熱狂と、日本の生産性の低さという現実の間には、大きなギャップが存在する。市場規模は2023年に1.4兆円を超えるという調査がある一方で(出所:株式会社富士キメラ総研<ソフトウェアビジネス新市場 2023年版>)、日本の労働生産性はOECD加盟国38カ国中30位と低迷(出所:公益財団法人日本生産性本部<労働生産性の国際比較2023>)。
その要因の一つが、BtoBの世界では、創り手と買い手をつなぐ「流通革命」が、いまだ起きていないことにあると言えよう。
この仮説を検証するために、別の角度からの視点と比較をしたい。この20年、私たちの消費の世界、すなわちBtoC市場で何が起きたのか。
かつて、無数の選択肢の中から本当に自分に合う商品やサービスを「探す」のは、私たち消費者自身の役割だった。しかし、テクノロジーがその常識を根底から覆した。Amazon.comは、私たちの購買履歴から好みを先回りして「おすすめ」を提示し、探す手間を省いてくれる。データを駆使して一人ひとりを深く理解し、その答えを最適なタイミングで差し出す。BtoCの世界では、テクノロジーによる効率化とパーソナライゼーションを極めることで、効率的な流通基盤が築かれたのである。
ひるがえって、BtoBの世界はどうだろうか。革新的なSaaSというプロダクトは、それを本当に必要とする企業へと、同じように民主的に届けられているだろうか。答えは、否だ。そこには、二つの大きな「壁」が存在した。
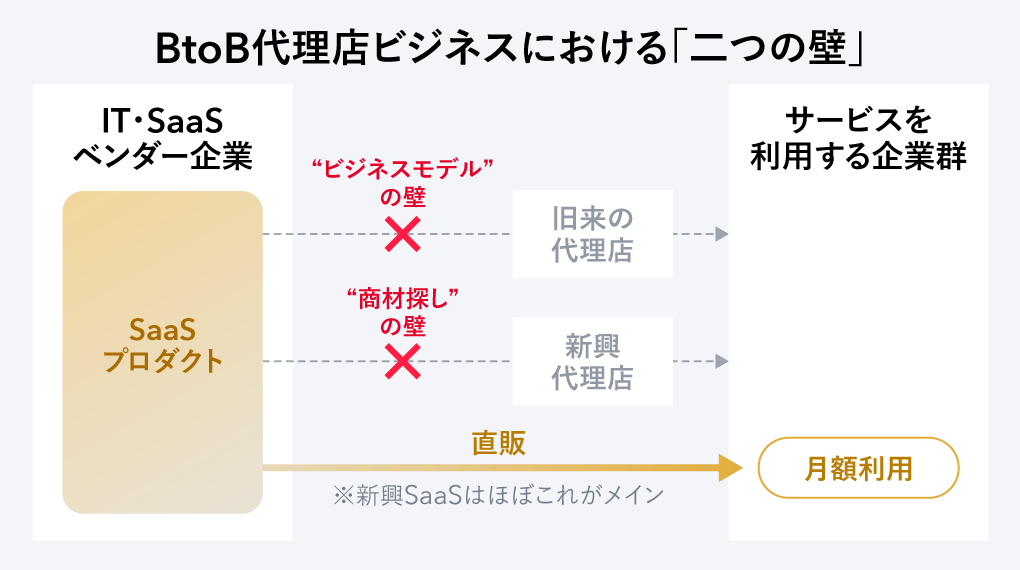
取材内容等を基にFastGrowにて作成
第一の断絶:旧来の代理店が抱える「ビジネスモデルの壁」
第一の断絶は、創り手であるSaaSベンダーと、旧来の巨大な販売代理店網との間にあった。これまで日本のIT流通を支えてきた彼らが、なぜSaaSという新しい商材をうまく扱いきれなかったのか。その理由は、彼らのビジネスモデルそのものに起因する。
従来の代理店の収益の柱は、商品を「仕入れて売る」ことで生まれる利ざや(マージン)だった。パソコンやコピー機といった物理的なハードウェアをメーカーから仕入れ、自社の在庫として抱え、それを売り切ることで売上を立てる。オンプレミス型のソフトウェアにおいても、この構造は同じだったのだ。この「在庫を動かす」という行為こそが、彼らの事業の根幹であり、長年かけて最適化された評価指標や業務フローも、すべてこのモデルを前提に構築されていた。
しかし、SaaSには、その「在庫」という概念が存在しない。月額課金が中心のサブスクリプションモデルは、仕入れや在庫管理を前提とした代理店の会計処理や販売管理システムとは、根本的に相性が悪いのだ。売り切りモデルに最適化された彼らの評価指標では、単価が低く、利益確定までに時間がかかるSaaSは「手間がかかる上に、儲からない商材」に見えてしまったのである。
もちろん、市場も手をこまねいていたわけではない。第一の断絶を乗り越えるべく、新しい時代の“届け手”が生まれ始める。時は2020年、そう、コロナ禍である。
対面営業が制限され、オンライン商談が一般化すると、SaaSビジネスを取り巻く環境は一変した。移動時間がゼロになったことで、一人のフィールドセールスが一日にこなせる商談のキャパシティは2〜3倍へと激増したのだ。だがそれがすぐに受注増につながるわけでもないというのが営業の難しさ。商談の「量」をこなせるようにはなったものの、その「質」、つまり成果につながる“良い商談”を安定して増やすことは、簡単ではなかったのだ。
ここに、新たなニーズが生まれる。SaaS企業の営業担当者が本来の強みである提案活動に集中できるよう、「質の高い、良い商談をセッティングしてほしい」という切実な願いだ。そして、この商機を捉え、SaaS企業の営業活動を「商談創出」という形で支援する、機動力の高い専門家たちが次々と独立・起業を果たした。彼らこそ、SaaS時代に最適化された、新しい販売パートナーの姿だった。
だが、皮肉なことに、一つの課題が解決されると、また新たな壁が立ちはだかる。
第二の断絶:新しい“届け手”が抱える「商材探しの壁」
この「新しい販売パートナー」たちの手元には、有り余るほどの時間と商談提案力がある。だが、そのリソースを最大限に活用するための、手持ちの「魅力的な商材」が圧倒的に足りなかった。彼らが抱えていた「売るべき商材を、どうやって見つけるのか」という課題は、市場の変化によって、より一層深刻なものとなった。
優れたSaaSは星の数ほどあれど、どのプロダクトが本当に市場で求められているのか、自分たちの営業・提案力を活かして商談設計ができるのか。それを知る術は限られていた。結果として、プロダクト開発に長けた「創り手」と、有り余るほどの販売能力を持つ「新しい届け手」は、互いの存在を渇望しながらも、出会うことができずにいたのである。
創り手は届け方を知らず、届け手は売るべきものを見つけられない──。
そこに登場したのが、『TAAAN』だった。
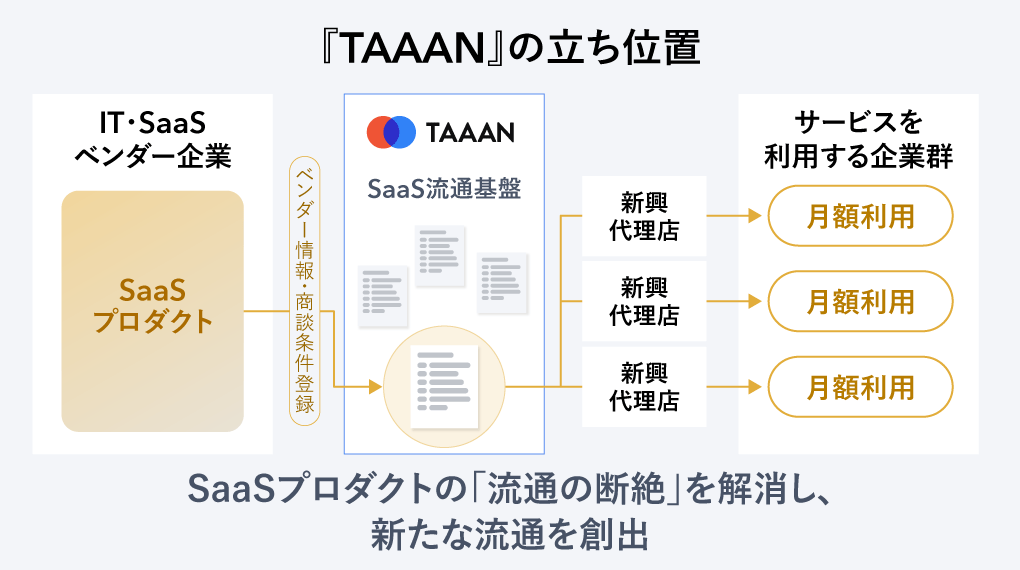
取材内容等を基にFastGrowにて作成
先述の二つの壁が、日本のBtoB市場の成長を妨げる一因となってきた。しかし、この裏側には、まだ名前のない、巨大な市場が眠っている。例えば、企業の営業活動を代行する「BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)」の国内市場規模は、2023年度には約4.8兆円に達し、2028年度には5.7兆円にまで拡大するという調査もある(出所:矢野経済研究所<BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場に関する調査を実施(2024年)>)。
今、KAENが挑んでいるのは、この巨大な市場の中に存在する「SaaS流通」という領域に特化し、テクノロジーの力でその非効率を解消する試みでもある。まずIT・SaaSベンダーとの距離感の近さから「日本企業に広く使われていくべき、SaaSを始めとしたイノベーティブな新規事業」の幅広く把握。そのうえで、キーエンスやリクルートで成果を残してきたような、無形商材のセールスに強みを持つメンバーで構成された新興代理店との独自のパートナーシップを広げてきた。
上図でも示したように、KAENだけが持つこの両面の“目利き”によって、日本各地でイノベーションが進む。
「ハイブリッド革命」の幕開け──『TAAAN』は“壁”をどう壊すのか
前章で明らかになった、二つの「流通における“壁”」。この根深い課題を乗り越えるべく、KAENは一つの解を提示した。それが、彼らの中核事業であるセールスインフラプラットフォーム『TAAAN』だ。
KAENが仕掛けるのは、単なるセールステックツールの提供ではない。それは、BtoC市場で起きたようなテクノロジーによる効率化と、BtoB市場で長年培われてきた人間による深い顧客理解。この二つをかけ合わせた、いわば“ハイブリッド型”の流通革命である。
その思想は、極めてシンプルだ。イノベーションを起こし得る優れたITプロダクトと、その価値を顧客に届ける「販売のプロフェッショナル」を、最も効率的に結びつけること。プロダクト開発に長けた創り手と、顧客開拓に長けた届け手。それぞれが自らの専門領域に集中し、その能力を最大限に発揮できるオープンな市場を創り出す。その思想を、代表の川田氏はこう語る。
川田僕たちは、「最高のプロダクト」と、その価値を最大限に引き出す「販売のプロ」が出会う場所を創りたかった。
これまで両者の間には、あまりにも多くの非効率なプロセスや情報の非対称性が存在していました。『TAAAN』は、その壁を取り払い、お互いがフェアに、そしてダイレクトにつながれる市場(マーケットプレイス)なんです。
その仕組みは、こうだ。まず、SaaSベンダー側が、「こんな企業と商談したい」という具体的な条件を『TAAAN』上に「求人票」のように掲載する。例えば、「請求書を月間300枚以上処理しており、なおかつ従業員数が50名以上の企業との商談に、1件あたり3万5,000円を支払う」といった具合だ。
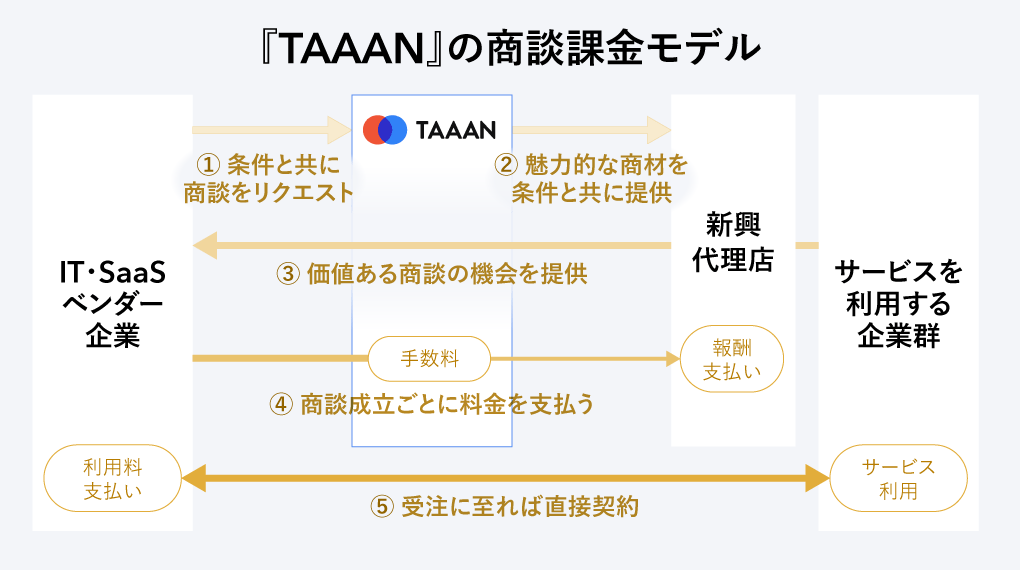
取材内容等を基にFastGrowにて作成
この「商談課金」というモデルこそ、KAENがもたらした特徴的な仕組みの一つだ。従来の代理店ビジネスでは、先述のように仕入れ額と販売額のマージンが儲けとなるのが一般的だった(多くの卸売事業と同じ)。最近になってSaaSプロダクトのパートナー営業に乗り出す事業者も増えているが、その場合も最終的な受注額の数パーセントを成功報酬として得るというモデルが多い。
KAENは、こうした仕組みに欠陥を感じ、「価値ある商談」を取引の対象として再定義した。これにより、SaaSベンダーは営業コストを予測可能なものに変え、リスクを抑えることもできるようになった。そして新興代理店(パートナー)は、自らの活動成果に直結した報酬を、迅速かつ確実に得られるようになったわけである。
旧来の常識を覆し、参加者全員の不確実性を低減するインセンティブ設計を実装したことこそ、このビジネスモデルの卓越した点だと言える。
『TAAAN』は、SaaSベンダーにとっては、これまでリーチできなかった顧客層への新しい販路を開拓するきっかけとなる。一方、新興代理店にとっては、「これまでの取引データから”売れる”と見込める商材」を、確実に仕入れることができるカタログとなる。
このシンプルな仕組みこそが、長らく続いてきた「流通の断絶」を根底から解決しうるのだ。
生態系のような好循環──ネットワーク効果によるプラットフォームの成長
『TAAAN』の価値は、単に創り手と届け手をつなぐ「マッチング」だけに留まらない。その本質は、プラットフォームに参加するプレイヤーが増えれば増えるほど、全体の価値が指数関数的に向上していく「ネットワーク効果」にある。そして、その効果を最大化させているのが、「テクノロジーの力で、人間の介在価値を最大化する」という、KAENの巧みな設計思想だ。取締役の梅木主道氏は、その核心をこう語る。
梅木『TAAAN』の本質は、テクノロジーと人間が、互いの強みを引き出し合うプラットフォームであることです。パートナーさんが足で稼いだリアルな顧客情報は、プラットフォーム上のデータを豊かにし、その蓄積されたデータが、またパートナーさんの次の提案をより鋭いものにする。その中からプロダクトに対するフィードバックも生まれ、IT・SaaSベンダーも事業を進化させていく。
この好循環こそが、我々の成長のエンジンなんです。

代表取締役川田氏(左)と取締役梅木氏(右)
具体的に、どのような好循環が生まれているのだろうか。
例えば、新興代理店のセールスパーソンたちは、近い領域のSaaSプロダクトを複数同時に抱えた状態で提案活動を行っていくことになる。その過程で、「どのような業種・業界に、どのSaaSが、なぜ刺さりやすいのか」というデータが、定量的に蓄積されていく。そのデータに基づいて、まず新興代理店の中での提案活動がどんどんアップデートされていく。
それだけではない。新興代理店から各IT・SaaSベンダーに対して、「○○な対応が求められている」といった客観的なフィードバックも届くのだ。ベンダー側はそのフィードバックを、プロダクト開発やフィールドセールスの現場で取り入れ、さらに良い事業へと進化させていくことになる。
これは、もはや単なる「取引の場」ではない。参加するすべてのプレイヤーが互いに学び、刺激し合い、そして共に進化していくエコシステムのようだ。『TAAAN』によって、イノベーションをめぐるエコシステム全体が底上げされていくのだ。一つひとつの商談の裏にある「生きた情報」を循環させ、市場全体をより賢く、より強く育てているわけなのである。
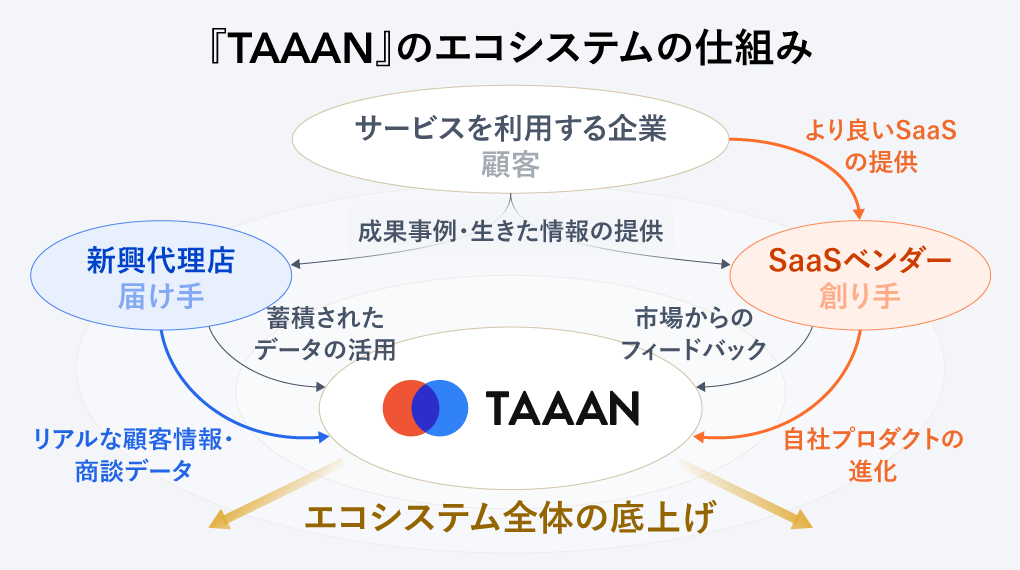
取材内容等を基にFastGrowにて作成
このKAENが描く生態系という構想は、単なる理想論ではない。すでに『TAAAN』は、市場での確かな手応えを示す、具体的な数値を叩き出している。
特筆すべきは、その市場カバー率だ。日本国内に存在する従業員50名以上の法人約10万社のうちなんと約3万社にまで、『TAAAN』のパートナーネットワークは何らかの形でアプローチし、その生の情報を蓄積しているという。これは、彼らが描く「市場の地図」が、構想ではなく、すでに実態を伴った資産となり、圧倒的な競争優位性を有していることまで示していると言えよう。
その成長性は、事業の軌跡にも明確に表れている。創業初期の苦戦を乗り越え、エンタープライズ企業が本格導入を始めたことを事業が軌道に乗る転機として、V字回復を達成。以来、売上は毎月、右肩上がりの急成長を続けているという。
そして、その価値を裏付けているのが、あるトップSaaS企業から買収の打診を受けたというエピソードだ。自社の成長に貪欲な市場のプロフェッショナルたちが、その生態系を強く求めている。この事実は、『TAAAN』が単なる便利なツールではなく、日本のBtoB市場で重要な役割を担いつつあることを示している。
強者のジレンマを打ち破る「戦略的選択」──なぜ“SaaSのプロ”が『TAAAN』を選ぶのか
これほどまでに市場の支持を集める『TAAAN』。そのプラットフォームには今、業界を牽引するSaaSのプロフェッショナルたちが、次々と集い始めている。しかし、なぜなのか。すでに自社で強力な営業組織を持ち、一定の成功を収めている彼らが、なぜ今、『TAAAN』を必要とするのだろうか。
その答えは、成功企業だからこそ直面する「ジレンマ」にある。多くのSaaS企業は、自社の努力でPMF(プロダクトマーケットフィット)を達成し、ARR(年間経常収益)10億円の壁を越えたあたりから、次なる成長の壁にぶつかる。これまで事業を牽引してきた、Web広告やコンテンツマーケティングといったインバウンドチャネルの効率が、市場の飽和と共に鈍化し始めるのだ。
次なる一手は、未開拓市場への「アウトバウンド戦略」である。しかし、ここに大きなジレンマが横たわる。
そもそも、多くのSaaS企業がこれまで頼ってきたWebマーケティングは、本当に万能なのだろうか。リスティング広告やウェビナーは、CPA(顧客獲得単価)の高騰に悩まされ、資料請求サービスでは、本当に会いたい企業の規模や部署とズレが生じることも少なくない。多額のマーケティング費用を投下しても、結局は“弾が当たらない”という課題に、多くの経営者が頭を抱えているのだ。
そして何と言っても「受注可能性が少しでもある会社に、できるだけ多く荷電する」というインサイドセールス手法に、非効率を感じたことのない人はいないだろう(もちろん、場合によっては投資対効果が合うこともあるのだが)。
ここで、先進的なSaaS企業は「戦略的な一手」を打つ。『TAAAN』を、単に「弱点を補うための外注先」としてではなく、「自社の強みをさらに伸ばすための戦略的パートナーシップ」として活用するのだ。
導入事例まとめ
- ペイトナー株式会社
導入初月から、商談数が1.5倍増(詳細はこちら) - 株式会社チームスピリット
商談獲得の基準を自分たちで決められ、成功報酬の発生条件をパートナー様に相談の上で自社で設定ができる(詳細はこちら)
※ほかの事例も含めたまとめページはこちら
選ぶのは、「自社営業か、『TAAAN』か」という二者択一ではない。「自社の強力なインバウンド営業はそのままに、『TAAAN』で未開拓市場へのアウトバウンドを仕掛ける」という、貪欲なセールス・マーケティング戦略である。『TAAAN』は、低リスクかつスピーディーに、新たな市場へ挑戦するための、有効な手段となる。
この戦略的選択によって、彼らが手にするのは、目先の商談だけではない。『TAAAN』を通じて、これまで自社の営業努力だけでは手の届かなかった地方都市や特定業界といった未開拓市場(ホワイトスペース)に対する、自社プロダクトの受容性を低コストで検証できる。そして、その活動から得られる「法人の生きた購買データ」は、彼らにとって次の事業戦略を練る上で、貴重な指針となるのだ。
『TAAAN』を選ぶこと。それは、営業努力の放棄などでは決してない。成功企業が次のステージへ飛躍するために、自社のコア事業にリソースを集中させつつ、新たな成長エンジンを手に入れるという、高度な戦略的判断なのである。
そして、その戦略的判断を後押ししているのが、KAEN自身の組織力だ。
『TAAAN』の事業責任者を務める畠中潤氏は、パーソルキャリアとオンリーストーリーでそれぞれ泥臭いセールスの経験を積んできた猛者である。そしてFringe81(現Unipos)でエンタープライズセールスやそのマネージャーを務めてきた佐藤魁氏が、グロースパートナーという立場で、新興代理店を全力で支援する。このように、ベンチャー・スタートアップにおける現場やマネージャーの経験を持つメンバーが集まり、切磋琢磨しながら、新たなビジネスモデルの実現とグロースに邁進しているのだ。
彼らが、単にプラットフォームを運営するだけでなく、その知見を活かしてIT・SaaSベンダーの成長戦略そのものに深く入り込み、伴走する。だからこそ、先進的なSaaS企業は、安心して自社の未来を託すことができるのだ。
新たなビジネスインフラへ──KAENが拓く、日本経済の未来
TAAANがもたらす変革は、単に「SaaSを売りやすくする」という次元に留まらない。その先に見据えるのは、日本の産業構造そのものをアップデートし、挑戦するすべての企業と個人にとっての「インフラ」となる未来だ。
そして特筆すべきは、KAENがこの壮大な挑戦を、極めて筋肉質な経営基盤の上で推進している点。創業からわずかな期間で、すでに一人当たりの売上高は国内トップクラスのスタートアップに匹敵する水準に達し、高い利益率を確保しているという。これは、彼らのビジネスモデルがいかに効率的で、スケーラビリティを持つかの証明に他ならない。
この強固な収益基盤があるからこそ、目先の利益に追われることなく、次なる未来へと大胆な投資を続けることができるのだ。KAENの挑戦は、ここからが本番である。
目指しているのは「成長産業向けのバーティカルなプラットフォーム」だ。IT・SaaSベンダーも、新興代理店も、これからの日本経済を牽引していくような高成長を続けていく存在である。だが今の日本ではまだ、その支援が不十分なままだ。
成長産業で挑戦を続ける企業たちに対し、営業・マーケ支援、人材、さらにはセキュリティ・金融なども含めさまざまな観点からのバックアップを行い、その成長をさらに押し上げていく。そうすることで、これまでの日本ではなかなか起きてこなかったような大きなイノベーションが当たり前になるような社会を創ろうとしているのだ。
そのために『TAAAN』の未来図として描くのが、蓄積した膨大な購買データを活用した「『BtoB版AdWords*』とも呼ぶべき、新たなマーケティング基盤」への進化だ。
*……Googleが提供してきた、検索エンジン上を主な掲出箇所としたウェブ広告システム。現在のサービス名称は『Google広告』。個人の検索行動や購買データに基づいて広告を表示し、膨大な広告市場を築き上げてきたとされている
川田BtoCの世界では、巨大なプラットフォーマーが個人の購買行動データを独占し、それを基に巨大な広告市場を創り上げてきました。
僕らがやろうとしているのは、その法人版です。
「法人の購買データ」を核に、どの企業が、いつ、どんなサービスを求めるのか。そのデータを最も深く理解するプラットフォーマーになれれば、日本のBtoBビジネスにおける非効率な「探すプロセス」そのものをなくせるかもしれない。そうなれば、もっと多くの企業が本質的な価値創造に時間を使えるようになります。
この構想は、SaaS業界だけに留まるものではない。すでにSaaS業界の枠を越え、大手通信キャリアやメガベンチャーなども、『TAAAN』の法人開拓力に注目し始めている。さらにKAENは、金融機関や展示会といった、これまで接点のなかったチャネルとの連携も視野に入れる。あらゆる商流をプラットフォームに統合し、日本全体のビジネスを活性化させていく。
加えて、KAENが目指すのは、単一事業の成功ではない。挑戦する人々が、その情熱をビジネスの成功へと昇華させるために不可欠な、あらゆる機能を提供するインフラとなることだ。それは、ITプロダクトの流通であり、営業の仕組みであり、挑戦を支えるデータの基盤でもある。
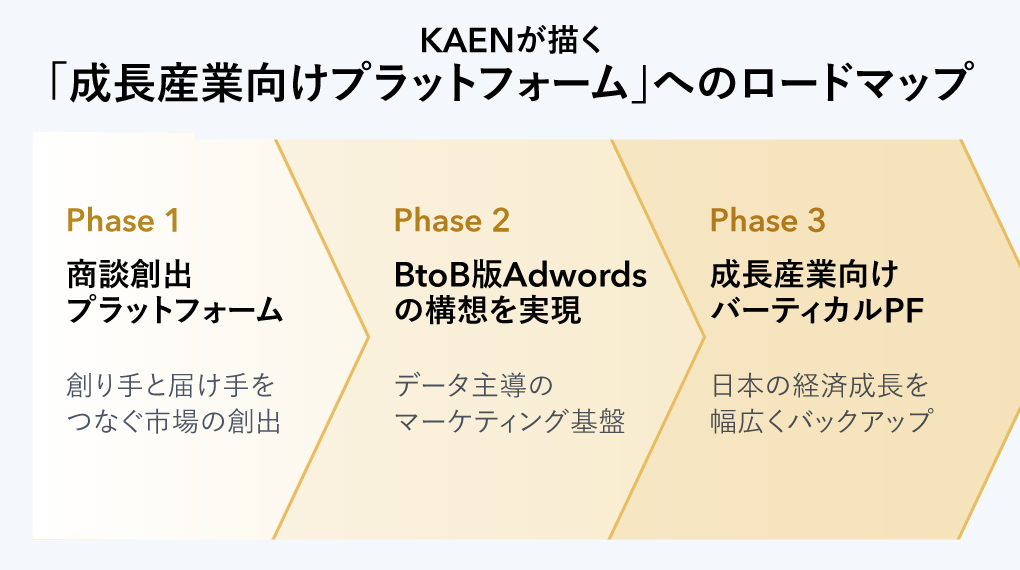
取材内容等を基にFastGrowにて作成
さらには、すでにHR領域で『Scout Base』、セキュリティ領域で『パスクラ』という事業をそれぞれ0→1フェーズで立ち上げている。ちなみに『Scout Base』を率いるのはFringe81やポジウィル、アビームコンサルティングといった成長企業を渡り歩いて経験を積んできた浦川雄志氏だ。新規事業部署にもまた、マチュアなメンバーが揃い、新たな挑戦を続けている。
こうした壮大な挑戦を、誰と成し遂げたいのか。KAENが求めるのは、単なる優秀な人材ではない。この国のビジネスが抱える構造的な課題を「自分ごと」として捉え、その解決に心を燃やすことのできる、未来を共に創る仲間だ。
日本の未来は、決して悲観的なものではない。眠っている専門性と、まだ見ぬ価値は、この国の至るところに存在する。それらを「つなぎ」、そのポテンシャルを解き放つことができたなら──。KAENの挑戦は、その希望を現実にするための、確かな一歩だ。
この壮大な挑戦に、あなたのスキルと情熱を賭けていくことを、想像してみてはいかがだろうか?これからもKAENは変わらず、優れたプロダクトと卓越した販売スキルをつなぎ合わせるような新たな仕組みを創り続け、日本経済を再加速させていくはずだ。
そして最後に伝えたいのは、この極めて合理的な戦略の裏には、創業者・川田の壮絶な原体験があったということ。なぜ彼はこの事業に人生を賭けるのか?その魂の物語を、次回の経営者単独インタビュー記事で明らかにする。
【各職種で採用を加速中:情報はこちらから】
こちらの記事は2025年07月24日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。


