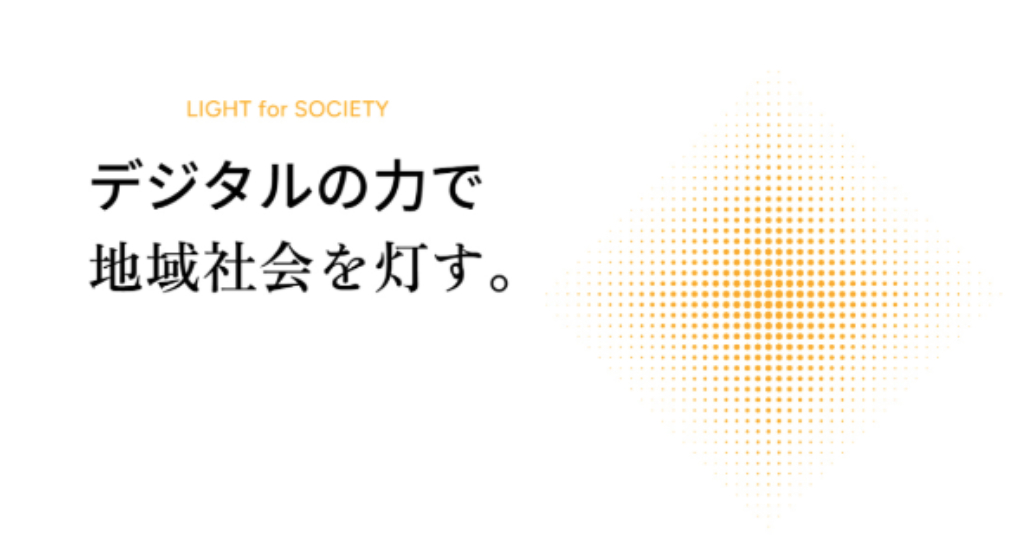連載株式会社ランプ
未知に、火を灯せ──京都発スタートアップ・ランプのCTO、カスタマーサポート&サクセスが語る、未完成だからこそ面白い“チームの化学反応”
Sponsoredスタートアップの魅力は、その「未完成」な状態にこそある。このことは、スタートアップの記事を2,000以上つくってきたFastGrow編集部の感覚としても、間違いない。まだ誰も知らない未来のスタンダードを、自らの手で創り上げる。その過程は困難に満ちているが、同時に、他では得られない興奮と成長の機会に溢れている。
京都を拠点に、累計10億円超の資金調達を実施し、SaaS『テイクイーツ』を2,500店舗以上に導入している株式会社ランプ(以下、ランプ)。同社は、今の輝かしい実績を「序章」と捉え、事業、組織、そしてカルチャーのあらゆる側面において「未完成」な未来のロードマップを明確に描き、それを共に歩む仲間を強く求めている。
本記事では、ランプが「未完成」をいかに成長の原動力とし、強固な組織文化と挑戦の機会を創出しているのか、事業を牽引する3名のキーパーソン、CTOの鈴木駿也氏、カスタマーサクセスの遠藤菜々子氏、そしてカスタマーサポートの桂裕幸氏の鼎談から深掘りする。そこには、あなたのキャリアにおける「次なる挑戦」を後押しするヒントが隠されているだろう。
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
「序章」に過ぎない成功──事業・組織・カルチャーに宿る“未完成”の現在地
鈴木ありがたいことに、事業規模も大きくなってきて、資金調達も進んできたのですが……私と(CEOの)河野の間では、日々、いろいろ迷っています(笑)。
というのも、たとえば社内メンバーとのコミュニケーション一つとっても。「あの言い方で大丈夫だったかな?」みたいな……。
日々、「経営者としての振る舞い方って、これで大丈夫かな。もっと気を遣った方がいいかな?もっと割り切ったコミュニケーションをした方がいいかな?」と、相談し合いながら、今後について考えているのが、私たちの今の実態です。

CTO 鈴木駿也氏
桂鈴木さんと河野さんが、そんな風に日々迷われているとは知りませんでした。近い距離で仕事をしてきた僕の感覚としては、むしろ逆の印象です。
河野さんは、会社を牽引するトップでありながら、非常に常識的で地に足が着いています。いい意味で“ぶっ飛んで”なくて現場と目線がずれていない、そんな良識ある感覚が彼の良さであり、ランプのカルチャーそのものだと感じています。

カスタマーサポート 桂裕幸氏
遠藤二人が話したことには共感しかないんですけど……一方で、河野さんについてはちょっと変というか、抜けていると感じる場面もたまにあります。この前、「自分で洗濯機を回したことがない」と言ってて、かなりの衝撃を受けました(笑)。

カスタマーサクセス 遠藤菜々子氏
鈴木それは知りませんでした。どうやって生きてきたんですかね(笑)。
決して建前ではない、温かくも率直な掛け合い。
この3名の、職種を越えたフラットな関係性こそ、ランプの成長を支える「チームのエンジン」に他ならない。 ランプが運営する『テイクイーツ』は、コロナ禍で顕在化したテイクアウト需要を捉え、わずか数年で導入店舗数を2,500以上にまで拡大した。多くの大手洋菓子ブランドも既に導入しており、チャーンレートは0.1%未満。その実績は確かなものだ。
しかしCEOの河野氏はもちろんのこと、この3名もまた、これらの成功に満足しているわけでは決してない。

取材内容等を基にFastGrowにて作成
ここでいう「未完成」とは、何かが不足しているなどの話ではない。素晴らしい未来を創造するポテンシャルを持ち、大きな挑戦の機会を内包しているということである。
まず事業面では、二つの異なるフェーズが同時に進行している。一つは、既に確固たる地位を築きつつある和洋菓子業界での話だ。前述した通り数多くの大手洋菓子ブランドが導入し、テイクアウト業態をとる店舗のインフラとして深く浸透し始めている 。ここでは、さらなる機能拡充によるエンドユーザーの体験向上や、それに伴う売上最大化など、より深い価値提供(深掘り)がテーマとなるだろう。
そしてもう一つが、次なるフロンティアである飲食店業界への本格的な挑戦だ。コロナ禍の緊急避難的なテイクアウト対応は落ち着き、今、飲食店が向き合うのは「テイクアウトをいかにして事業の柱に育てるか」という、より戦略的な課題。ここはランプにとって新たな勝ち筋を見つけ出し、仕組みをゼロから構築していく「0→1の挑戦」が数多く眠る「未開拓」な領域なのである。

組織面においても、河野氏をはじめメンバー達は「未完成」を楽しみながら進化を続けている。
現在(2025年8月時点)、約20名の少数精鋭チームでありながら、事業の急成長に伴う組織拡大の中で最適なチーム体制や役割分担を常に模索し、実践している。特にユニークなのは、カスタマーサポートとカスタマーサクセスの役割だ。
遠藤解約防止のカスタマーサポートやカスタマーサクセスというと、いわば提供価値における“負”をなくしていくというイメージになると思います。でも、そういった場面はほとんどありません。
もちろん、顧客が抱える課題を解決する「守り」の側面も重要だが、ランプの神髄はそこではない。和洋菓子業界でのさらなる深掘り、そして飲食店業界という未開拓領域への挑戦、その両方において、現状維持ではなく、顧客の売上成長を共に創り出す「攻め」のパートナーであることを自らの存在意義としているのだ(このことは次のセクションで詳しく掘り下げていく)。
さらにカルチャーも「未完成」だ。創業期から受け継がれる「イシュードリブン」の文化は浸透しつつも、より良いあり方を追求し、進化し続けている。これは、創業期からプロダクト開発と組織づくりの両輪を担ってきたCTO鈴木氏の思想が色濃く反映された結果だろう。彼がかつて感銘を受けたという「組織作りはプロダクト作りだ」という言葉の通り、課題(イシュー)を特定し、仮説を立て、最速で実装・改善していくアプローチが、プロダクトだけでなく組織文化そのものにも適用されているのだ。
これらの「未完成」な状態は、ランプのメンバーにとって、自らの手で事業、組織、そしてカルチャーを創り上げていく大きなチャンスとなっている。
「攻め」のサポートとサクセスで、拓く未来──“未完成”な市場を定義する役割分担
こうした「未完成」な事業や組織を創り上げる挑戦の最前線に立つのが、顧客と日々向き合うカスタマーサポートとカスタマーサクセスだ。今のランプ“らしさ”が、ここに見て取れる。
一般的なSaaS企業では(特にアーリーフェーズでは)解約防止が主なミッションとなることの多いカスタマーサポート・カスタマーサクセスだが、ランプではそうはなっていない。
その要因は大きく二つに分かれる。一つは、中核となるプロダクトが現場のニーズに強く刺さっていること。もう一つは、テイクアウト対応の現場には大きな伸びしろがあるということだ。
桂まず、『テイクイーツ』があるだけで、顧客の現場が確実にアップデートされます。予約電話への対応が不要になることで、わずらわしさも人的ミスのリスクも大きく減ります。そして追加注文が増え、売上も向上します。まずこの点で、ニーズを強く満たしています。
遠藤その上で、データを基に新たな売上向上施策を何度も提案するのが、カスタマーサクセスの仕事です。例えば、『テイクイーツ』への導線をWebサイトのどこに設置するかの提案や、受け取り可能日時を短縮するためのオペレーションの見直しなど、他社での事例を交えてお伝えしながら、お客様の事業が成長する方法を一緒に模索しているんです。

ランプでは、一般的にSaaSビジネスで多い「定額課金型」に加え、「売上連動型」も組み合わせたビジネスモデルをとる。遠藤氏を中心としたカスタマーサクセスが貢献すればするほど、ランプの売上が増えることにも直結するわけだ。
ただし、顧客の売上に直結するということは、それだけ深く顧客の販売現場に入り込むということである。いわゆるオンボーディングも、一筋縄ではいかない。それを牽引するのがカスタマーサポートの桂氏である。
桂一番大きな私の役割は、導入を 決めていただいた顧客企業に対して、 その運用開始までの手助けをすること。ですがそもそも、「このように使ってくださいね」と伝えるだけで進むわけではないのです。
まず、顧客の事業規模やブランド・商品数、利用目的を、改めて丁寧にヒアリングします。そうすることで、何をどのようにテイクアウトで売るのか、それらによる売上目標はどれくらいを目安にするのか、という部分を考えた上で、逆算して最適なアカウント設計を提案していくんです。そこがすりあって初めて、取り扱う商品や受け取り可能時間などの詳細設定をプロダクト上で行い、実際にテイクアウト注文用のページを完成させ、店舗側でもPCやタブレットで注文管理ができる運用体制を整えていきます。

印象的だったのは、決して効率だけを追求するものではないということだ。たとえばバックオフィス支援のSaaSであれば、解決すべき課題が多くの企業に共通しており、ある程度はマニュアル通りの初期設定が重要になるのが一般的だろう。
しかし『テイクイーツ』のように、和洋菓子店や飲食店の現場での利用を考えると、そうではないオンボーディングの意識も重要になる。エンドユーザー向けに大切につくり上げてきたブランドの世界観や、購入体験を、具体的にしっかり把握し、壊さぬよう個別の対応を考えていかなければならないのだ。
そんな試行錯誤によって、単なる効率化ツール以上の価値、すなわち「新たな販売チャネルの確立」まで一気に実現でき、顧客の売上貢献にまでつながっていく。
桂ここからが本番。実際に『テイクイーツ』を毎日触って運用いただく店舗担当者や店長、本部の統括担当者に向けてじっくり説明し、スタートダッシュをサポートします。その後も店舗や本部からの細かな問い合わせに答えたり、エンドユーザーからの質問にも対応したりと、まさに「サポートセンター」的な役割を担っています。
そして導入後、「サポートセンター的役割」とは異なる目線で徹底支援するのが、カスタマーサクセスだ。
遠藤導入企業の販売データを常に確認して、売上増加につながるアイデアを模索しています。とはいえ、決して堅苦しい関係ではありません。Slackの共有チャンネルで、「この商品、Webサイトのこの写真に変えた方が絶対売れますよ!」とラフに投げかけたり、時には「今日近くまで来たので、お店の様子見に来ちゃいました」と顔を出したり。
そうした毎日の動きに加え、特に売上規模が大きいブランドに対しては毎月定例ミーティングを実施しています。データを基に「ここをもうちょっと変えたら売上を伸ばせるんじゃないか」といった提案をしています。
たとえば、オンライン注文サイト上での商品紹介のちょっとした工夫や、ブランドのトップページからテイクアウトのページへの動線の最適化など、事業全体を俯瞰して課題解決に貢献します。
また新しい機能がリリースされた際には、その情報を顧客に正確に伝え活用を促すことも、もちろん重要なミッションです。アップセルでの売上責任もありますから(笑)。
たとえば、遠藤氏は大手洋菓子ブランドへの提案事例を挙げ、商品ラインナップの拡充や当日受け取りの最適化といった具体的な施策で月次売上を1.5倍にまで引き上げたケースがあるのだという。
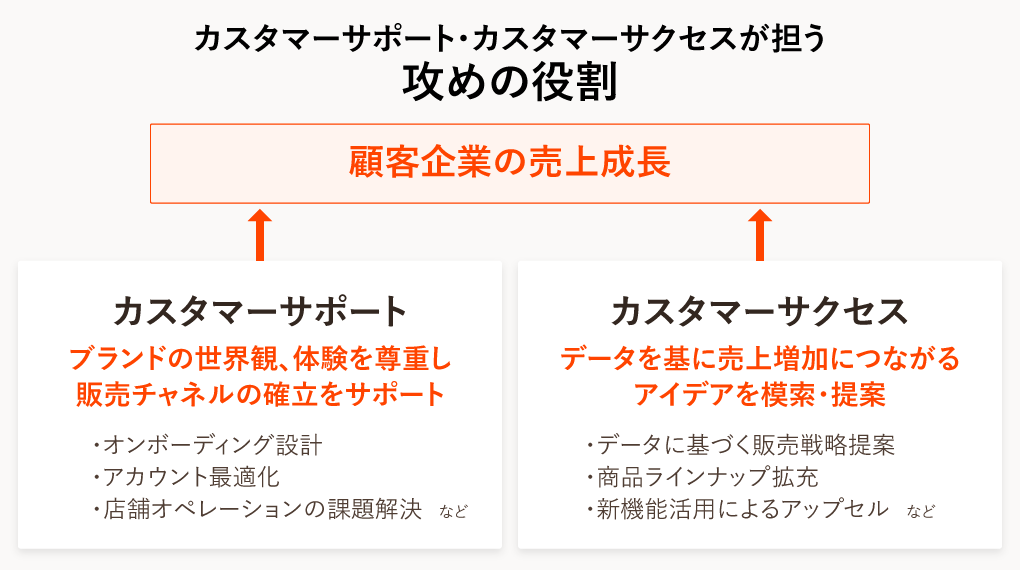
取材内容等を基にFastGrowにて作成
飲食店にとってのテイクアウトチャネル拡大は、単なる業務改善ではなく、新たな売上モデルを構築する「新規事業」に等しい。その支援を現場で行うのがカスタマーサポートであり、カスタマーサクセスだ。
前の記事でCEO河野氏が語った通り、『テイクイーツ』には「食のShopify」とも呼べるようなマルチプロダクト化のロードマップがある。その実現のためにも、既存機能をドライブさせる桂氏や遠藤氏の存在は非常に重要なのだ。2025年6月にリリースされた新プロダクトの「ECカート」に加え、データ活用によるCRM、需要予測といった未来のサービス構想の真価も、この二人にかかっていると言っても過言ではないかもしれない。
「未完成」を楽しむ組織──“カオス”を成長機会に変える「イシュードリブン」文化
ここからは、カスタマーサポート・カスタマーサクセスがランプの事業成長に貢献するもうひとつの側面を見ていく。いやむしろ今回はこちらがメインのトピックとなるだろう。それは「プロダクト全体の進化への貢献」について、だ。
ランプのプロダクトは、創業期からその全体を見てきたCTOの鈴木氏を中心に動く。核にあるのは、マイクロマネジメントを排し、本質的な問いを立てる「イシュードリブン」なカルチャー。最終的な判断はCTOやPdMが行うが、その前に「的確なイシューを見抜く」ためにも、現場の声を拾い集めるカスタマーサポート・カスタマーサクセスの貢献は不可欠だ。
鈴木「要望共有会」という定例の会議体で、カスタマーサポート・カスタマーサクセスそれぞれが顧客企業の現場で直に収集してきた機能要望や困りごとを聞いています。
ここで聞く要望の「毛色」が、サポートとサクセスで違うのが面白いところなんです。どちらも顧客の売上を伸ばすための「攻め」の要望なのですが、その角度が異なります。
カスタマーサポートからは注文を受けてから商品を準備し、お客様に「受け渡す」という、日々の業務、オペレーションを磨き込むことで、“今の売上”を取りこぼさないための攻めの提案が多く上がってきます。いわば、顧客体験の土台を盤石にする視点ですね。
一方でカスタマーサクセスからは、「どうすればもっと売れるか」「売上を最大化するために、どんなカスタマイズが必要か」といった、事業成長の新たな可能性を切り拓く、“未来の売上”を創り出すための攻めの提案が中心です。
こうした両面からのインプットがあるからこそ、プロダクトの死角がなくなり、事業全体がバランス良く成長していける。この状態は非常に健全だと感じています。

桂鈴木さんの言う通り、私からは現場のオペレーションに関する要望を上げることが多いですね。ただ、お客様からいただいた要望をそのまま右から左へ流すことはしません。必ず「なぜ、この機能が必要なんですか?」「これがないと、現場ではどんなミスや非効率が生まれているんですか?」と、その背景にある“Why”を深く聞くようにしています。
なぜなら開発チームが本当に知りたいのは、「〇〇機能が欲しい」というWhat(何)だけではなく「それを実装することで、現場の誰の、どんなペイン(痛み)が解消されるのか」という、手触り感のある情報だからです。その解像度を極限まで高めてパスすることが、私の役割だと考えています。
遠藤カスタマーサクセスから伝える要望では、「どうやってもっとたくさん売るか」の部分が多いですね。
ただし、点でのサポートにしかならないものなら、プロダクトの機能として開発する必要はありません。意識しているのは、その要望が一社の顧客に継続的に価値を提供する“線”の施策になるのか、あるいは、他の多くの顧客にも横展開できる“面”の機能へと昇華させられるか、という視点です。そのために、お客様の言葉の裏にある本質的な課題は何かを常に考え、多面的に話を聞いています。そして「これがあることで、プロダクトとして本当に良いものになるのか?」という問いを自分に投げかけていますね。

異なる役割のメンバーから寄せられる、毛色の違う要望を丁寧に吸い上げ、事業へのインパクトを横断的に検証することで、開発の優先順位を判断する。言葉でこのように書くと簡単なことのようだが、そんなことは決してない。『テイクイーツ』は売上に直接影響を与えるため、顧客企業それぞれから目標・KPIを達成するための切羽詰まった要望が届くこともある中、すべてにスピーディーに対応できるわけではない。
最近になって開発が進んだ「特定営業日の設定機能」。この機能には、多くの顧客から寄せられた切実な声と、それに対して「いかに最適な形で応えるか」を悩み抜いたチームの、実直な姿勢が映し出されている。
桂以前から、たとえば「クリスマスの時期だけケーキの受け取り時間を長くしたい」「土用の丑の日だけうなぎを手渡しする営業時間を変えたい」といった要望が、それぞれのお店の事情に応じてかなり多く届いていました。
ただ、それをプロダクトチームにどう伝えて、開発の優先度を上げてもらうか……それが難しかったんです。PdMがジョインする前は、要望を伝えても、その重要度や背景をうまく伝えきれていなかったのかもしれません。

遠藤私も飲食店やカフェ業態のお客様からこうした要望をお聞きすることが何度もありましたね。書き入れ時の売上増加には不可欠な機能だと捉えられていたので、なんとかしたいと考えていました。
正直、以前は要望を伝えても開発の優先順位がどうなっているのか分からず、もどかしい時もありました。でも今は、全社で見られる要望管理リストができて優先順位が可視化されたことで、私自身の“もやっと感”はかなり減りましたね。
鈴木お二人が言う通り、2023年ごろから明確に要望として把握していました。もちろん、すぐにでもお応えしたかった。ただ、当時はまず、誰もが安心して使えるようにシステムの土台を安定させ、より多くのお店に価値を届けるための基本的な機能開発に注力していました。中途半端なものを出して、かえってお客様を混乱させるわけにはいかないという思いがあったんです。
そんな風向きが変わったのが2025年に入ってから。顧客基盤が安定し、チームの体制も整ったことで、「お客様が最も売上を伸ばせる書き入れ時に、ご不便をおかけしているこの状況を、これ以上看過できない」という機運がチーム全体で高まりました。サポートやサクセスのメンバーが代替策の説明に費やす時間や、お客様が失っているビジネスチャンスを数字で突き合わせた結果、「今こそ、最高の形でこの機能を届けよう」という結論に至ったんです。

桂以前は「基本の営業時間を長くして、対象の日以外では、朝と夜の時間帯の在庫をゼロにする」といった、仕組みをハックするようなご利用もされていたんです(苦笑)。ご不便をおかけしている心苦しさもありましたし、エンドユーザーさんを混乱させてしまうリスクも感じていました。
そうまでして『テイクイーツ』を使い続けてくださるお客様の期待に応えられていない自分たちが、本当にもどかしかったです。
鈴木ですが、優先度を上げてからは早かったですね。開発チームの地力も上がっていましたし、スコープを最小限に絞るために桂さんたちと密に連携した結果、検討開始から1カ月程度でリリースにこぎつけることができました。
長くお待たせしてしまった分、自信を持ってお届けできる機能になったと思います。お客様の声を、ようやく最高の形でサービスに反映できた。チーム全員がそう感じています。
冒頭から言及してきたように、ランプはまだまだ「未完成」である。だからこそ、こうした機能開発一つとっても、その周辺に大きな伸びしろが存在し、その伸びしろを埋めるような動きによって、これまでにない価値を生み出せる。それが顧客の成長、ひいてはランプ自身の成長やメンバー個々人の成長にもつながっている。
「未完成」なリーダーだけでなく、「未完成」なプロダクトと、「未完成」なチーム。だが同じ未来を見て、同じ気持ちで挑戦し続けているからこそ、一歩ずつ進んで新たなイシューを見つけ、それを乗り越え、次のイシューに向かっていけるのだ。
「完成された組織」を飛び出した2人。
なぜランプの“未完成”に惹かれたのか?
では、その「イシュー」が眠る現場の最前線に立ち、あえてこの“未完成”な環境に飛び込んできたメンバーは、何を考え、何を見ているのか。
ビジネスサイドを牽引する桂氏と遠藤氏、二人の“個”の物語に光を当てたい。その選択の背景には、多くのビジネスパーソンが一度は直面するであろう、キャリアにおけるリアルな葛藤と希望が映し出されている。
カスタマーサポートを率いる桂氏は、老舗の楽器メーカーという全く異なるカルチャーの世界からやってきた 。伝統的なビジネスモデルが根付き、良くも悪くもルールや仕組みが固定化された世界といえるかもしれない。彼はその中で、一つの「渇望」を抱えていた。
桂前職は歴史ある会社で、ルールや仕事の進め方がしっかりと決まっていました。それは安定している反面、自分で考えて何かを変えていく、という経験は少なかった。もっと「当事者意識」を持って、ゼロから何かを創り上げる仕事がしたい、とずっと思っていました。
ランプは、まさにルールも決まりもない“未完成”な状態。だからこそ、「お客様のために何ができるか」を自ら考え、サポートの仕組みを一つひとつ自分の手で構築できる。このことに、強烈なやりがいを感じています。それに、CEOの河野もCTOの鈴木も、いわゆる“ザ・スタートアップ”という感じのギラギラしたタイプじゃない。いい意味で人間臭い感じもあって、やりやすいんです(笑)。
だからなのかどうかはわかりませんが、私のような異業種からの人間の意見にも真摯に耳を傾けてくれて、一緒になって組織を創ってくれる。この関係性が、すごく心地いいんですね。

決められた役割をこなすのではなく、自ら役割を定義し、創造していく。桂氏はランプの「未完成」さの中に、失われかけていた仕事への「当事者意識」を取り戻すための、最高の環境を見つけた。
桂氏とは対照的なキャリアを歩んできたのが、カスタマーサクセスを担う遠藤氏だ。彼女は東大医学部を経て、新卒で国内有数のSaaSスタートアップであるSansanへ。セールス、CS、開発といった組織体制も高度に仕組み化されている。いわば「完成された」ような環境だ。その中で彼女は、SaaSビジネスのプロとして確かな経験を積んだ。だが、そこでの「分業体制」が、次第に彼女をある種の“もどかしさ”へと導いていく。
遠藤前職は役割の分業が徹底されていて、私は新規営業担当として、受注したらCSチームに引き継ぐのがミッションでした。もちろんそれは組織として合理的ですが、個人的には「もっと長くお客様の成功に寄り添いたい」というもどかしさも感じていました。
その点、ランプはプロダクトも組織もまだまだこれからのフェーズ。自分の働きかけ一つで、プロダクトの未来を大きく変えられる可能性がある。そして何より、セールスからサクセスまで一気通貫で顧客に伴走し、その成長をダイレクトに感じられる。そこに、前職とは全く違う面白さを感じたんです。今はカスタマーサクセスの仕組みづくりや人員増強にも挑戦させてもらえていて、「未完成」な部分すべてが、私にとっては挑戦の機会になっています。

完成されたレールの上を走るのではなく、自らレールを敷く面白さ。彼女は未完成な今のランプに、自身の介在価値を最大化できる、広大な“余白”を見出したのだ。
二人の物語が示すのは、ランプという組織の「不完全さ」が、いかにして個人の成長と挑戦の機会へと転化されているか、という事実だ。それは、自らのキャリアの可能性を模索する多くの人々にとって、一つの確かな道筋を示しているのかもしれない。
「完成」を待つな、自ら創れ。ランプが“未来の仲間”と描く、終わりなき挑戦のロードマップ
桂氏や遠藤氏のような、自らの意志で「未完成」を成長の機会へと転換する挑戦者たち。ランプは今、そんな仲間を心から求めている。
同社が見据えるのは、単なるテイクアウト予約システムの提供者という現在地ではない。蓄積された「データ」を最強の武器に、需要予測やCRMといった新たな価値を提供する“食のShopify”という壮大な構想。それもまた、まだ具体的なロードマップが引かれたばかりの「未完成」な状態だ。
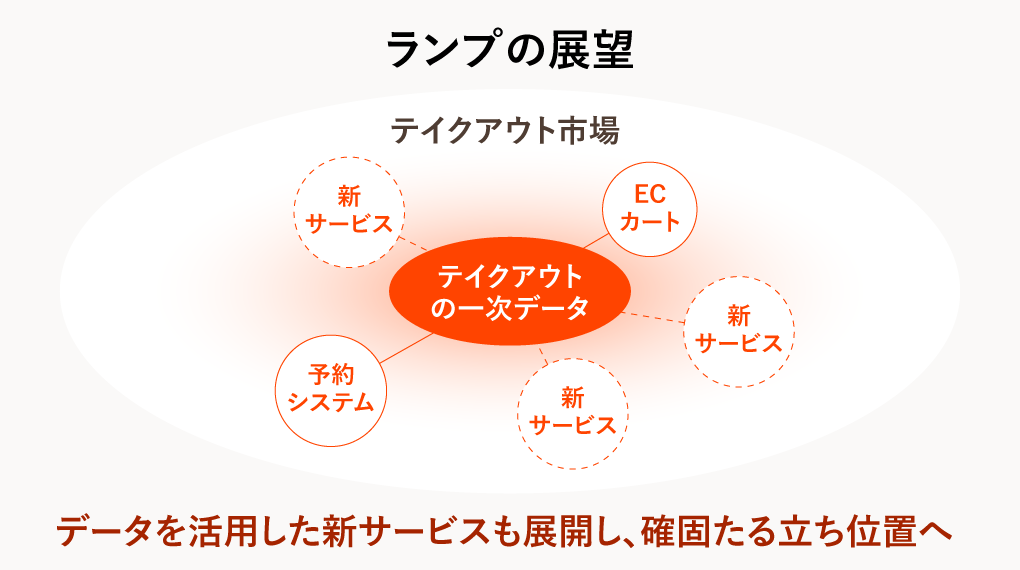
取材内容等を基にFastGrowにて作成
鈴木僕らが密かに抱いている野望は、「地方発スタートアップのロールモデル」になることです 。わざわざ東京に行かなくても、地方からだって日本中、そして世界をあっと言わせる事業は創れる。それを僕らが証明したいんです。この挑戦は、僕たちだけでは成し遂げられません。
完成された組織の歯車になるのではなく、「未完成なチーム」に必要不可欠な屋台骨となれ──。ランプが求めるのは、完璧なスキルセットを持つ人材ではない。この終わりなき挑戦を、共に楽しみ、悩み、そして創り上げていく「仲間」だ。
そうした環境で働くリアルな手触り感を、桂氏はこう語る。
桂地方発の事業ですが、もはや垣根は関係ありません。
今、全国の顧客企業様から、良い声も悪い声も直接私の耳に届きます。それをしっかり受け止めて、どうアクションにかえていくか……一つのミスが顧客の事業、ひいては人々の食卓の幸せを左右するかもしれない。そんな責任と意義を感じられるとともに、大きなやりがいを覚えています。

全国に広がる顧客と向き合う中で、遠藤氏は今、自身の役割、そしてチーム全体が新たなフェーズに移行していることを感じている。
遠藤一人ひとりが成果を出し、事業を伸ばしていくんだという強い気持ちはもちろんあります。ですが、これからも個人の成果だけに目を奪われることなく、チームとしてどう成果を最大化していくかという、より俯瞰的な視点が重要になるフェーズです。
(カスタマー)サクセスもサポートも、セールスもプロダクトも、これからさらに人数を増やし、全国各地のテイクアウト支援を広げていく。今の役割分担は決して完成されたものではなく、新たな役割を自ら考え、創っていく必要があると感じています。
桂まさにそうですね。カスタマーサポートとカスタマーサクセスの役割が明確に分かれたのも、1年ほど前にエンタープライズの顧客が増え始めた際に、必要に迫られてのことなんです。今後も顧客企業の層は拡大していきますから、同じように新たな役割を増やし、チームも再編していくでしょう。
そんな「未完成」さの中での挑戦ができる環境は、地方にはまだ少ないんじゃないかと思います。少しでも興味を持ってもらえたら、ぜひ話を聞いてほしいです。

ランプの成長は、単なるビジネスモデルの成功ではない。それは、事業・組織・カルチャーのあらゆる側面において「未完成」な状態を、挑戦と成長の機会として捉えること。そして、CEOの揺るぎない「大義」に共鳴するチームが、顧客の「不便」を「喜び」に変え続けていることの証左だ。
「地方の日常」に眠る課題に真摯に向き合い、テクノロジーと人間力で「食の未来」を灯す。その壮大なビジョンを追求するチームは、まだ完成していない。
だからこそ、面白い。
事業は、なぜ大義を必要とするのか──劣等感、為替変動、チーム解散…ランプCEO河野匠が語る、”凡事徹底”から生まれた経営哲学
【各職種で採用を加速中】
こちらの記事は2025年08月26日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。