【徹底解剖】PoCで失敗する3つの理由──「業務前提の維持×現場の無関心×配置不安」を乗り越える、ソルブレインのAI/DX実装戦略
Sponsored多くの日本企業がAI活用やDX実現への新規プロジェクトに取り組むが、その大半は「PoC(概念実証)止まり」に終わる。試験導入はするものの、本格的な実装・運用には至らず、投資対効果の測定が難しい状況が続くケースが多い。
この課題に対し、仙台発のベンチャー・ソルブレインには、大手エンタープライズ企業から次々と声がかかっている。2023年、同社は三井物産からの出資を機に、事業を大きくシフトした。日本を代表する企業のAI活用支援/DX支援に乗り出し始めているのだ。社員60人(2025年11月記事公開時点)の規模ながら、エンタープライズ企業の業務フロー再設計から実装まで、PoCを超えて成果を出し続けているのだ。
その背景にあるのが、グロースマーケティング支援で培った「全体最適」の視点だ。顧客企業のビジネス全体を俯瞰し、広告運用からセールス、顧客満足度向上まで一気通貫で成果にコミットする。この思想が、データ分断に悩むエンタープライズ企業のニーズと合致した。
注目すべきは、入社4年目の25歳社員が大手通信企業の業務フロー再設計に関わるなど、エンタープライズ案件の現場で若手も活躍している点だ。本記事では、ソルブレインがなぜPoCを超えて実装まで進められるのか、その実装プロセスの実態に迫る。
- EDIT BY TAKUYA OHAMA
人口減少で揺らぐ事業継続。エンタープライズもいよいよ事業の全体最適へ
ソルブレインの事業が「グロースマーケティング支援」からAI活用支援/DX支援へとシフトし始めたのは、2023年4月の三井物産からの出資が転機だった。これを機に、顧客層がエンタープライズ企業に移行し、同社の事業は大きく進化することになる。
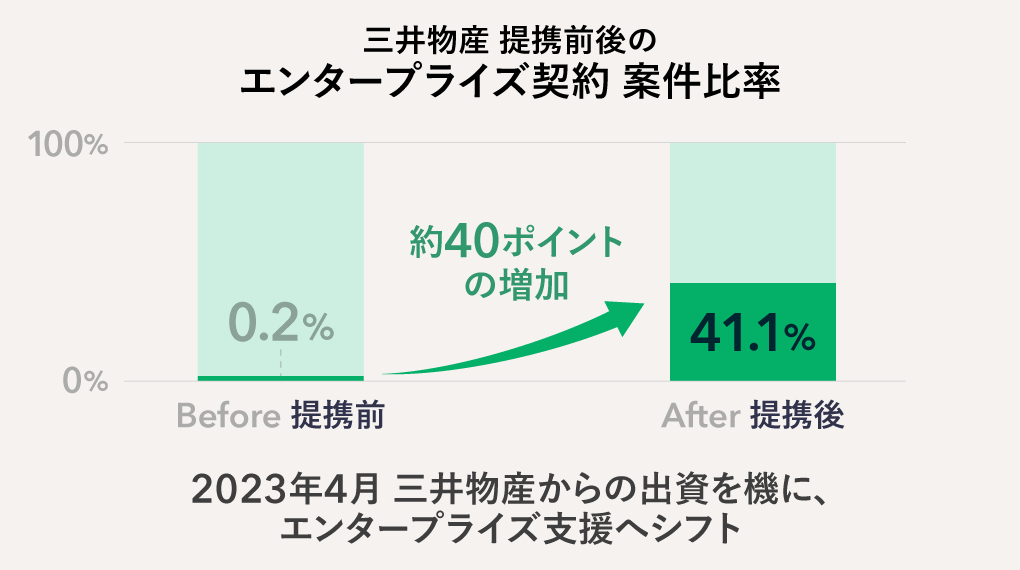
取材等を基にFastGrowにて作成
グロースマーケティングとは、顧客企業のビジネス全体を俯瞰し、広告運用からセールス、顧客満足度向上まで一気通貫で成果にコミットする手法だ。単なるマーケティング支援ではなく、顧客企業の売上・利益の最大化を目指す。

(「ヤフーとソルブレインが語る 〜データを活⽤し持続的な成⻑を実現するグロースマーケティングとは〜」から抜粋)
このアプローチ自体は、エンタープライズ企業からも高い評価を得ていた。だが、エンタープライズ特有のビジネス慣習との間に、いくつかの障壁があったのだ。
最大の障壁は、「予算管理の違い」である。
ソルブレインは成果報酬型、つまり顧客の売上が伸びなければ自社の収益も発生しない契約形態を採用してきた。これは顧客の成果に徹底的にコミットする姿勢の表れだが、エンタープライズ企業にとっては予算のボラティリティ(変動幅)が大きすぎる。なぜなら、年間予算を固定し、1年間のスケジュールを確定させて進めるエンタープライズの予算管理とは、根本的に相容れないからだ。
そしてもう一つの障壁が、「データ活用の制約」だろう。
エンタープライズ企業の多くは、長年の組織拡大の過程で部門ごとに最適化された業務システムを構築してきた。その結果、各部署が独自のデータ基盤を持ち、全社横断でのデータ統合においては進んでいないケースも見られる。いわゆる「データ分断」の状態だ。
これは、エンタープライズ企業特有の構造的課題である。事業が安定的に成長している間は、部門最適でも十分に成果を上げることができた。各部門が独立して高い専門性を発揮し、それぞれの領域で顧客価値を提供してきた歴史がある。

取材内容等を基にFastGrowにて作成
しかし、今やその前提が変わりつつある。
日本の人口減少により、労働力の確保が困難になってきたのだ。強固な事業基盤を築いてきた世代が引退していく中、人手不足がビジネスの継続性に影響を与え始めている。ここにきて、エンタープライズ企業は「事業構造の効率化──つまり、限られた人材で最大の成果を出す体制づくり」が不可欠だという機運に包まれている。
こうした背景から、エンタープライズ企業はAIを活用した新規事業開発や既存事業モデルの抜本改革の取り組みを増やしている。その中には、単独で進めるのみならず、ベンチャー企業やスタートアップとパートナーシップを組み、「PoC」の形で進める例も多い。
だがそれでも、多くのプロジェクトはPoCで止まる傾向にある。
そんな中、社員60人の仙台発ベンチャー・ソルブレインに声がかかっているのだ。
その理由の核は、グロースマーケティングで培った「全体最適」の視点にある。バリューチェーン全体を見渡し、顧客企業のビジネスの再設計から手がける。この姿勢が、データ分断という構造的課題を抱えるエンタープライズ企業が求める支援と合致したのである。
ソルブレインが注力するのは、エンタープライズ企業の業務フローを実際に変革し、数値で成果を証明できる支援だ。システム導入だけに留まらず、事業構造そのものに踏み込む。個別の業務効率化を超えて、全体最適を追求する。この視点こそが、兼ねてより同社の差別化要因となっている。
だが、視点だけでは実装には至らない。多くの企業がPoCで止まる中、ソルブレインには実装まで進める独自のアプローチがあった。
PoCを超える3つの実装条件「AIありきの業務再設計」×「現場WILL」×「配置転換」
そのアプローチとは、大きく3つに分けられる。「AIありきでの業務フロー再設計」「現場のWILL(意欲)の見極め」、そして「配置転換を前提とした丁寧な説明」である。
その根底には、グロースマーケティングで培った「テクノロジーで最適解を提供する」という思想がある。バリューチェーン全体を見渡し、顧客企業のビジネスそのものを再設計する。その上で、テクノロジーを使って解決する。この発想こそが、ソルブレインの強みなのだ。
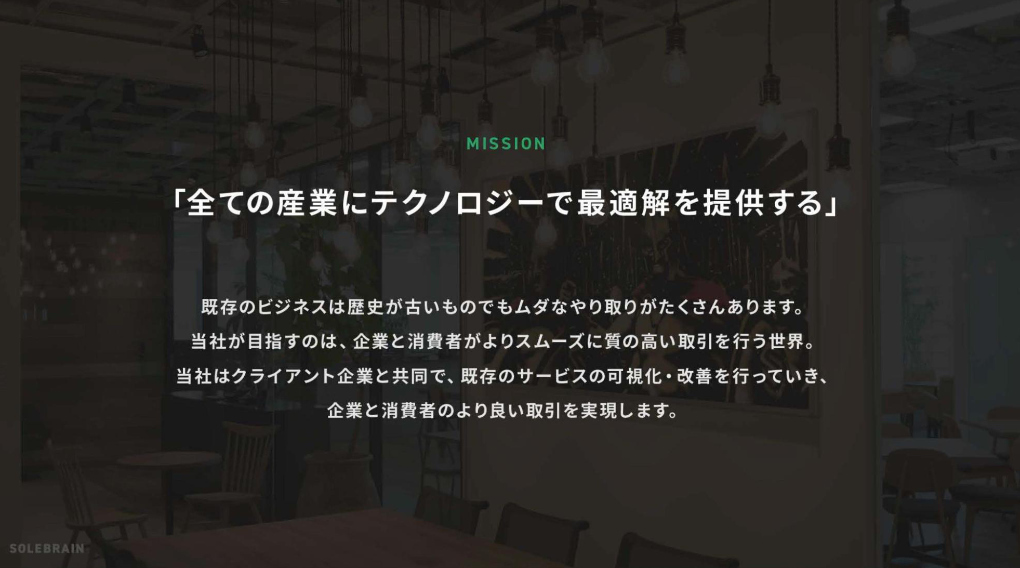
提供:株式会社ソルブレイン
ソルブレイン代表の櫻庭氏はこう語る。
櫻庭AI活用支援/DX支援がPoCで止まるパターンと、実装まで進むパターンには明確な違いがあります。AIありきで業務を再設計できる企業はうまくいく。一方で、「今の業務フローをそのままAIで置き換えてください」というアプローチは、高確率で失敗する傾向にあると感じています。

ソルブレイン代表・櫻庭 誠司氏の経営者像は以下に詳しい
「稼ぐ理由が、君の天井を決める」──ソルブレイン櫻庭×STUDIO ZERO仁科対談。利益の先にある、経営者の使命
典型的な例が、ダブルチェック・トリプルチェックの問題だ。
本来、AIとシステムを組み合わせれば人的ミスはほぼ防げる。にもかかわらず、「念のためダブルチェックを残しましょう」という判断をする企業は多い。これは既存業務フローに引きずられた結果であり、そのまま置き換えようとするパターンの典型だ。
AIありきで業務を再設計できるかどうか。これがPoCで止まるか、実装まで進めるかの一つの境目として挙げられる。先述の通り、ソルブレインはグロースマーケティング支援の時代から、「顧客企業に業務フローの再設計を提案し、本質的な改善を追求する」というメソッドを持っていた。手段がAIに変わっただけで、その本質は変わらない。

取材等を基にFastGrowにて作成
では、ソルブレインはどのように現場のWILLを見極めるのか。
櫻庭氏はプロジェクトを開始する際、必ず顧客の現場に問いかける。「今の業務フローを説明してください。そして、『この業務をなんとか良くしたい』というWILL(変革への意欲)はありますか?」と。現場メンバーが自分ゴトとしてWILLを持っていないプロジェクトを成功させるのは容易ではない。
興味深いのは、WILLをはっきり持つのが若手社員に多くみられるという点だろう。PC操作に抵抗がなく、伸び代のある業務フローに対して自然と疑問を持てる世代である。ソルブレインによれば、実際のプロジェクトに参加した社員の約95%が、むしろチャンスだと捉えて前向きに取り組んでいるとのこと。
では、WILLさえあれば全てうまくいくのだろうか。答えは、否だ。大手企業でAI活用やDXの実現を進める際、最大の障壁となるのが「業務変革への不安」である。業務プロセスが再編されれば、特定の部署の業務量が大幅に減少する可能性が高い。これまでその業務に従事してきた社員にとって、「自分の役割はどうなるのか」という疑問が浮かぶのは当然だろう。
ここで重要なのが、配置転換を明確に打ち出すことである。
社員が「雇用が維持されるのか」という不安を抱えたままでは、プロジェクトに協力的になれない。情報も出にくくなる。うまくいっている企業は、プロジェクトの初期段階で「雇用は維持されます。配置転換という形で、より価値の高い業務に就いていただきます」と明示する。社員の納得感が得られるまで、丁寧に説明することが不可欠だ。
その点、ソルブレインはこの説明の仕方にも工夫を凝らしている。AI化を「キャリアアップのチャンス」として捉え直してもらうのだ。
AI活用は今後あらゆる業界・職種で必須のスキルになる。既存の業務では得られない「AI活用の実績」という知見が蓄積されるのは、今後のキャリアにとって大きな武器になる。こうした文脈で説明すると、前向きに取り組む社員が大半を占めるようになるそうだ。
「AIありきでの業務フロー再設計」「現場のWILLの見極め」そして「配置転換を前提とした丁寧な対応」。この3つが揃って初めて、PoCを超えて実装まで進められる。
では、そんなソルブレインの実装によってどれほどの成果が生まれているのか。実例をみていきたい。
5つの事例から見る、業務フロー全体の再設計
ソルブレインが手がけるAI活用支援/DX支援は、多岐にわたる業務領域で成果を上げている。エンタープライズ企業の複雑な業務フローに対し、AIで再設計することで、劇的な効率化を実現しているのだ。
事例1:上申業務の効率化
エンタープライズ企業では、複雑な社内ルールに則った「上申プロセス」が必要だ。しかし、この上申書類の作成に多くの時間が費やされ、上司からの差し戻しも頻発に発生する。事業推進のスピードが損なわれるケースも少なくない。
ソルブレインはここに対し、社内規定の適合性チェックや、承認を得やすい上申文章の自動作成を行うAIシステムを提供している。これにより、差し戻しやルーティン作業が大幅に削減され、事業活動のスピードと質が向上する。
事例2:社内プレゼン資料作成の効率化
多くの企業で、社内向けプレゼン資料の作成に膨大な時間が費やされている。特に、企業ごとのデザインルールに則った資料を一から作成する負荷は大きい。
ソルブレインが提供するのは、簡単な指示に基づきAIが自動で構成・生成するシステムだ。顧客のデザインルールに即したパワーポイント資料を生成することで、全社員の資料作成時間を短縮し、社員が本来注力すべきコアな業務に集中できる環境を実現する。
事例3:社内問い合わせ対応の効率化
人事・経理等の管理部門には、社員からの数百件規模の質問・問い合わせが日々寄せられる。この対応負荷は大きく、担当者の生産性を大きく阻害する要因となっている。
これに対し、ソルブレインはRAG(検索拡張生成)技術を活用したシステムを提供している。社内規定やマニュアル、カスタマイズした情報を根拠情報として参照させることで、LLMのハルシネーションを抑制した正確な回答を自動生成する。膨大な社内問い合わせ業務の削減・効率化と、回答品質の均一化を図る。
事例4:窓口応対業務の自動化
顧客対応の窓口業務も、大きな工数を要する領域だ。会員情報変更などの定型的な手続き対応に、多くの人員が割かれている。
ソルブレインが提供するのは、AIアバターによる自動応対システムだ。ディスプレイ上のAIアバターが音声対話で顧客の用件をヒアリングし、そのデータをカスタマーセンターへ連携する。LLMによる自然なコミュニケーションで応対を完結させることで、顧客体験を維持しつつ、窓口業務の負荷を軽減する。
事例5:受注〜発注業務フローの最適化
複数社が関わる受注から発注までの業務フローは、手作業での入力・作成工程が多く、時間とコストがかかる。
ソルブレインはここに対し、AIを活用した業務フロー最適化を提供している。手作業で行っていた工程をAIで自動化することで、大幅な工数削減を実現する。
これらの事例に共通するのは、「既存業務の効率化」に留まらない視点だろう。
ソルブレインは、AIツールの導入前に必ず問う。「そもそもこの工程は必要か」「人間がやるべき作業とAIに任せる作業をどう切り分けるか」。単なる自動化ではなく、業務全体を見渡した上での最適化を提案する。この姿勢が、エンタープライズ企業から“継続的に”高い評価を得ている理由である。
では、これほど多様な案件を、社員60名の組織でどうやって回しているのか。この大規模な実装を可能にしているのは、ソルブレイン独自の組織体制だ。
「デザイン駆動型開発」と「営業組織の体系化」。社員60名でエンプラ実装を回す組織体制の核心
同社のユニークな組織体制のポイントとは2つ。「デザイン駆動型開発」と「営業組織の体系化」にある。
デザイン駆動型開発とは、深い洞察に基づいた仮説検証とプロトタイプ開発を高速で実行し、顧客との対話を通じて真の課題を炙り出すアプローチだ。ソルブレインでは、PM、セールス、エンジニア、UI/UXデザイナーが一体となって顧客の現場に深く入り込む。エンジニアも現場に足を運び、業務の実態を直接把握する。こうした現場主義が、データだけでは捉えきれない暗黙知や構造的な課題を可視化する起点となっている。
重要なのは、机上の空論に終わらせないことだ。プロトタイプを顧客に見せ、即座にフィードバックを得る。「この工程は本当に必要か」「なぜこの確認が存在するのか」──顧客との対話を通じて、表面的な要望の裏にある本質的な課題を炙り出していく。そして修正したプロトタイプを再び提示し、またフィードバックを得る。この思考と実装のサイクルを限りなく速く回すことで、顧客自身も気づいていなかった「真の問い」が明確になるのだ。
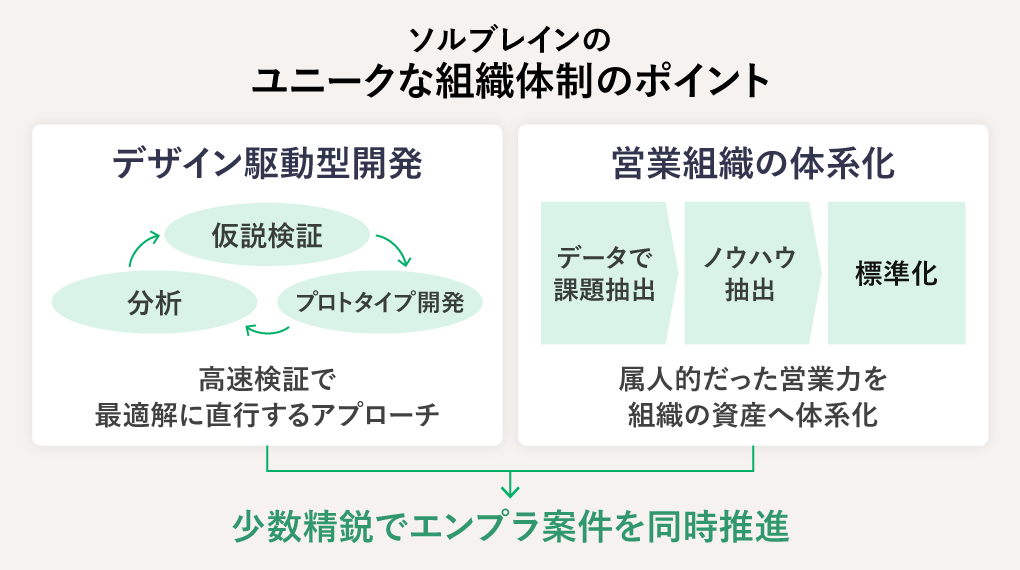
取材内容等を基にFastGrowにて作成
「問いの確定」──ここにソルブレインの本質があると言えるのではないか。顧客のビジネスに深く入り込み、暗黙知を解き、真に解決すべき問いを見つけ出す。そして、プロトタイプという具体的な形で検証を繰り返しながら、最短距離で最適解にたどり着く。このアプローチが、PoCを超えた実装を可能にしているのだろう。
だが、こうした案件を組織として継続的に獲得するには、もう一つの柱が必要だった。それは、営業力の仕組み化である。
これまでソルブレインの営業最前線を担ってきたのは、創業者の櫻庭氏ただ一人だった。顧客のビジネスを深く理解し、経営層すら気づいていない本質的な課題を見抜く。その卓越した営業力が、同社の成長を牽引してきた。しかし、事業の急速な拡大に伴い、櫻庭氏の営業力を組織として再現できる体制の構築が新たな課題として浮上する。
そこで、2024年に一人目の営業担当として参画したのが辻氏だ。辻氏は三菱電機でIoT製品営業として全国トップの営業成績を記録し、トレジャーデータではインサイドセールスのマネージャーとしてデータドリブンな営業の仕組み化を推進してきた実績を持つ。
辻氏がソルブレインで取り組むのは、「データを活用した営業プロセスの標準化」と「営業手法の体系化」である。これまで櫻庭氏の経験や直感に基づいていた課題発見のプロセスをデータで可視化し、再現性を高める。顧客ごとに個別対応していたノウハウから、横展開できる要素を抽出・整理し、テンプレート化を進める。こうして、誰もが一定の成果を出せる営業体制を構築しようとしているのだ。

写真提供:株式会社ソルブレイン
“カリスマ営業”の仕組み化は実現可能か?──急成長ベンチャーでゼロから営業組織を創る、ソルブレイン・辻の挑戦
現場に深く入り込み、プロトタイプで検証を繰り返す開発体制。櫻庭氏の営業力を、データとテクノロジーで組織全体の資産に変えていく仕組み。この二つが揃ったことで、ソルブレインは社員60名ながら複数の大手エンプラ案件を同時に推進できるようになったのだ。
エンタープライズとの長期的な信頼構築。拡大期に「断る勇気」を持つクオリティ担保の仕組み
しかし、急速な拡大は新たな課題も生んでいる。エンタープライズ企業からの引き合いが殺到する今、櫻庭氏が最も警戒しているのがクオリティの低下である。
エンタープライズ企業の顧客対応には、中小企業とは異なる特性がある。中小企業の場合、サービス品質に課題があれば比較的すぐにフィードバックがある。だが、エンタープライズ企業の場合、クオリティに課題があっても即座にフィードバックがあるとは限らない。むしろ、次回の契約更新時に静かに判断を下す傾向がある。
これによる難しさは、ソルブレイン側でクオリティ低下を検知しづらいという点だ。拡大期には、経営陣の目が届かない案件が増えていく。そのタイミングで、クオリティが下がっても気づけない。これが最大のリスクだ。
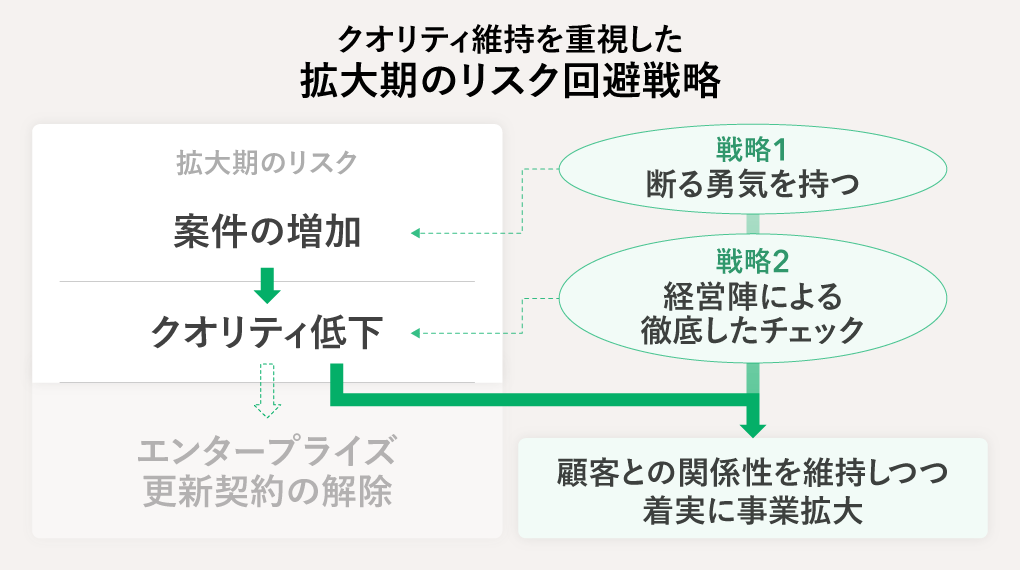
取材等を基にFastGrowにて作成
だからこそ、ソルブレインはクオリティを担保した上での組織拡大を最優先している。エンタープライズを中心に多くの企業から声がかかり、事業の状況は良い。だが、そこに浮かれず、「断るものは断る」という勇気を持つ。あくまでクオリティを重視し、顧客のニーズに応えるという調整が極めて重要だと位置づけているのだ。
具体的には、経営陣が全案件のクオリティチェックを継続している。これまでエンタープライズ案件で若手が大きな失敗をした事例はまだない。だが、それは今、経営陣がクオリティチェックをしているからに他ならない。
櫻庭氏は、この体制を維持しながら組織を拡大する方針だ。急速な拡大でクオリティが下がれば、エンタープライズ企業は黙って離れていく。その結果、せっかく築いた信頼関係が崩れてしまう恐れがある。だからこそ、組織拡大のペースをコントロールし、クオリティ維持を最優先する。
どこまでも「顧客への価値提供」にこだわる、経営者・櫻庭氏らしいスタンスと言えよう。 そしてこの姿勢こそが、大手エンタープライズから継続的に引き合いを受ける理由でもあるのだ。
過去一番の進化スピード環境。エンタープライズ需要に応える事業ドメインの進化
クオリティを重視しながら拡大を続けるソルブレイン。その先に見据えているのは、事業ドメインそのものの進化だった。同社は今、事業ドメインが進化する過渡期にある。
グロースマーケティングの本質、つまり顧客の売上/利益に包括的にコミットし続ける、全体最適を追求する。この軸は変わらない。だが、手段としてのDX、AI、技術の多様性は一気に広がった。顧客ニーズに応じて事業ドメインを進化させる──まさに今が、そのタイミングなのである。
実際、三井物産からの出資を機に、顧客ドメインはエンタープライズへとシフトしている。売上構成比でも、エンタープライズの比率が大幅に増加した。
グロースマーケティング支援からAI活用支援/DX支援へ。顧客も中小企業からエンタープライズへ。この2年間でソルブレインは大きな転換点を迎えている。櫻庭氏は、この変化をどう捉えているのか。
櫻庭過去一番で進化のスピードが速い環境に身を置いている。エンタープライズから多くの声をかけていただいている今は、大きなチャンスです。

生成AIを触っている人なら誰でもわかるが、進化のスピードはあまりにも速い。ChatGPTが登場してから、わずか2年足らずで生成AIは業務の現場に浸透し始めた。この変化のスピードは、インターネット黎明期を彷彿とさせる。
AI活用支援/DX支援という領域は、まだ誰も確立していない。だからこそ、今この瞬間に関わる意味がある。ソルブレインは、グロースマーケティングで培った「業務フローの再設計」という強みを武器に、この新しい領域で先行者優位を築きつつある。
もちろん、櫻庭氏は競合の脅威も認識している。ところが、興味深いのはその競合がAIベンチャーではないという点だ。
理由は明確。多くのAIベンチャーにとって、エンタープライズ企業のガバナンスやセキュリティポリシーをクリアすることは、時間と体制整備を要する課題となる。ソルブレインが三井物産との提携でエンタープライズ企業の「お作法」を理解しているのに対し、ベンチャーがこの壁を乗り越えるには時間がかかる。
一方で、櫻庭氏が脅威と見ているのが、コンサル寄りのSIerだ。彼らは長年、エンタープライズ企業の業務フローを構築してきた。だからこそ、「改善の余地がある業務フロー」がどこにあるかを知っている。AIという新しい武器を手に、本気で取り組めば、強力な競合になりうる。
ソルブレインにとって、今が勝負の時だ。 ライバル企業が本気で動き出す前に、エンタープライズ企業での実績を積み上げ、先行者優位を確立できるか。 この1-2年の勝負が、同社の未来を決めるのである。
事業形態が進化しても、顧客の売上/利益創出にコミットする軸はブレない(by FastGrow編集部)
ここまで見てきたように、ソルブレインは中小企業向けのグロースマーケティング支援から、大手エンタープライズのAI活用支援/DX支援へと事業ドメインを大きく進化させてきた。
多くの企業が事業ドメインを変える際、表層的な技術トレンドに流されがち。AIが流行れば「AI支援」と名乗り、DXが流行れば「DX支援」と名乗る。だが、本質的な価値提供が曖昧なまま事業を広げれば、顧客からの信頼は得られない。
しかし、ソルブレインは違う。
グロースマーケティング支援で培った「顧客の事業成長に包括的にコミットする」という根幹を、AI活用支援/DX支援にも貫いている。技術は手段であり、目的は常に「顧客の売上/利益の創出」である。この軸がブレないからこそ、三井物産を始めとするエンタープライズ企業から、数年にわたる共同事業として声がかかるのだ。
FastGrow編集部としては、ソルブレインは今後も確実に成長していくと見ている。理由はやはり、顧客への価値提供がブレないからだろう。
事業ドメインが変わっても、顧客の事業成長に本気でコミットする姿勢が変わらない企業は、長期的に信頼を獲得し続ける。今回のソルブレインの事例は、AI/DX時代における事業再設計のヒントを提供しているのではないだろうか。
こちらの記事は2025年11月27日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
編集
大浜 拓也
株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。
おすすめの関連記事
FastGrow厳選!2025年版 急成長テックカンパニー8選──テクノロジーで社会課題を解決する、次世代の成長企業たち
「小売特化型・2軸成長モデル」で競合ともマーケットを共創!?──ブランド創造×コンサル支援で売上325億円を生むイングリウッドの成長戦略
IPOラッシュのITコンサル領域に、数千億円のホワイトスペース──事業家集団Entaarが挑む、エンタープライズITの構造改革
- 株式会社Entaar 代表取締役 CEO
【反則級AI SaaS?】導入企業が月1,000万の売上純増!エンドユーザーの脳内を“透視”する8名の精鋭、InsightXの正体とは
売上を追うな、熱狂を追え──元ベインの共同代表2人があえて“2年間の沈黙”を選んだ、合理的過ぎる理由【InsightX共同代表・中沢×佐竹】
- 株式会社InsightX 共同代表CEO
“フルスタック”は死語?AI時代に「100倍の成果」を。顧客現場で汗を流すエンジニア像「FDE」の生々しすぎる実践事例【InsightX岸本・中塚・和田】
- 株式会社InsightX CTO
最強の競合は“現状維持バイアス”だ──「未来の体験」と「現場の理屈」を接続するInsightXのエンプラセールス【CEO佐竹×Sales今江】
- 株式会社InsightX 共同代表CEO
コード一行もない「紙芝居」での調達から、売上ゼロの2年間──DNXと共に耐え忍んだInsightXの、“泥臭すぎる検証”から得た勝ち筋とは
- 株式会社InsightX 共同代表CEO

