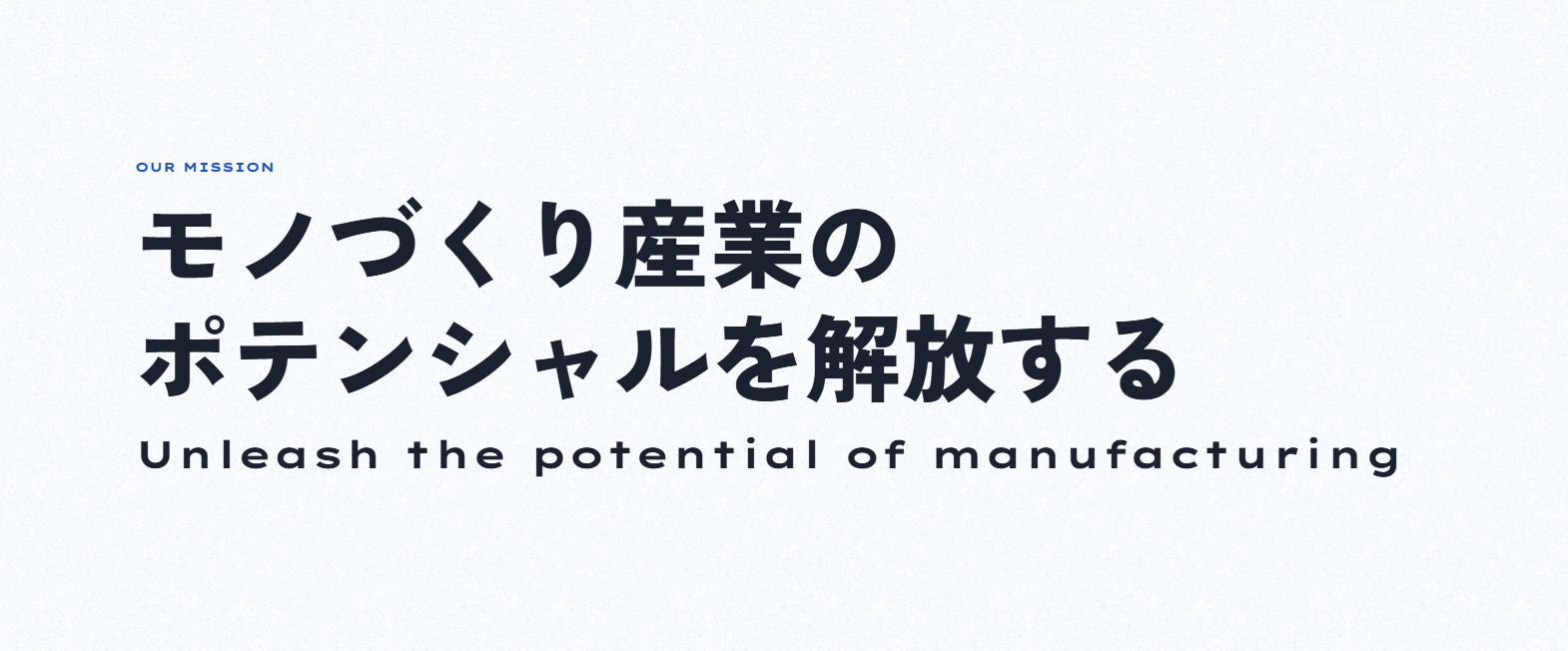連載新生キャディ
600人でも「0.1合目」の異次元な挑戦──“3年で数十個”のハイグロースなプロダクト開発に挑むキャディの開発組織
Sponsoredキャディという急成長スタートアップにまつわる“謎”を追う本連載。今回でラストの記事となる。これまで3記事にわたって、「事業は伸びているのか?」(主に1記事目で詳述)、「“成果が全て”なドライなカルチャー?」(主に3記事目で詳述)といった謎を紐解いてきた。そしてまだ残る謎が、「組織はもう出来上がっている?」である。2記事目でCHRO幸松氏にも語ってもらったが、今回はさらに深く掘り下げていく。
創業8年目、従業員600人超、累計調達額217億円(2024年12月時点)。これらの数字だけを見れば「ある程度ポストも埋まり、組織としては整っていそうなスタートアップ」という印象を受けるだろう。ところがキャディのメンバーたちは「全くもって未完成なスタートアップ」と口を揃える。
その理由を今回は、CTO小橋氏を筆頭とした3名の開発組織キーパーソンたちの言葉から探る。
ここ1年ほどの間にも、スタートアップやメガベンチャーでCTOやテックリードといった重責を担ってきたメンバーが集まり続けているキャディの開発組織。この3名は、どのようにこの開発組織を牽引し、どのようにプロダクト価値を高めていこうとしているのだろうか?そして、本当に「製造業AIデータプラットフォーム構想」は実現しうるのだろうか?
そういった疑問を持ち3名に話を聞くと、「構想の実現にはすでに手応えがある」「100を超えるプロダクトアイデアもある」「ただし、現在の600人規模では、メンバーの数が全く足りない」といった現状が見えた。今のキャディのプロダクトや開発組織の“未完成さ”に迫っていこう。
- TEXT BY YASUHIRO HATABE
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
壮大なミッションと事業構想だからこそ、「そう簡単に完成するわけない」
FastGrowでも2024年11月に公開した同社解剖記事で、「市場規模や課題の大きさからするとまだまだ未完成な状態」と紹介させてもらった。その詳細について小橋氏は「誰も想像したことがない壮大なミッションを掲げているので、そう簡単にプロダクトや組織が完成するわけないじゃないですか」と、笑顔で、そして熱を込めて語り始めた。

キャディ株式会社 取締役CTO 小橋 昭文氏
小橋600人の組織というと、スタートアップとしては大きいと感じる方もいるかもしれません。けれど、数千兆円の市場規模がある、世界中の製造業の顧客に価値を届けていきたいわけですから、人数としては全然足りないんです。
藤倉今後3年で数十個のプロダクトを、グローバルに提供していく計画ですからね。今の時点ではそのうちの数個を開発している段階ですが、すでにリソースが足りていないという感覚です。
桑名もちろん、リソースが不足しているから人数を増やす、というだけではありません。ビジネスサイドのメンバーも話していた通り、個々人のポテンシャル解放もかけ合わせることによって、構想をより早く実現して、顧客により早く価値提供できる強い開発組織になっていけるはずなんです。
3名が話す「未完成」のゴールはどこにあるのか?
それはキャディのミッション「モノづくり産業のポテンシャル解放」を実現するための新構想『製造業AIデータプラットフォーム』(『CADDi Manufacturing』と『CADDi Drawer』の事業統合からの未来像、公式発表はこちら)だ。(連載1記事目にも紹介が詳しい)。

取材内容等を基にFastGrowにて作成
小橋キャディがつくる製造業AIデータプラットフォームは、過去の経験を情報として積み上げて資産とするもの。過去の情報があるからこそ、次の世界をつくるところに投資ができるわけです。
常に将来を見て、「今日やった仕事は明日やらずに済む」という世界観を実現したいと思っています。そのために、今日やった仕事を明日やらなくていいくらい「しっかり積み上がっている」構造を描きたい。
「我々は苦労したのだから、君たちも苦労すべき」といった職人的な考え方が今でも見受けられますが、「もう、そんな時間(猶予)はないですよ」と思うんです。今の製造業には定年間際の方々が多くいらっしゃるので、知識と経験の継承を急ピッチで進めていかなければならない。このタイミングで、「人の働き方そのもの」から変えていかないと、産業として成立しない状態に陥ってしまうかもしれない。それくらいの危機感を抱いており、またそれを防ぐような事業を作っていきたいんですよね。
藤倉すでにいくつかの新規アプリケーション開発に着手していて手元には100を超えるアイデアがあります。先ほどお伝えしたとおり、今後3年間のうちに数十個はリリースする計画を立てています。
この壮大なプラットフォームの上では、一つひとつのアプリケーションがそれぞれユニコーン企業並みのポテンシャルを持つことになります。そしてそれらが相互に影響し合い、価値を高めていくんです。

キャディ株式会社 VPoE 藤倉 成太氏
桑名事業統合前と比較して、エンジニアリングの事業成長に対する貢献余地も格段に飛躍したと感じています。なぜなら、アプリケーションをいくつも開発し、プラットフォーム上で連携させていくわけですから。
こんなにも刺激的で、ワクワクする開発に関われる組織は、そうそうないと感じています。

キャディ株式会社 Growthグループ Documentチームリーダー 桑名 泰輔氏
壮大すぎるが「手応えはある」。製造業のカルチャーをも変えうる「製造業AIデータプラットフォーム」
これまでのFastGrowの記事でも、この構想と、それらが製造業に与えうるインパクトについて語られている。
とはいえ、あまりに壮大すぎる構想ではないか…という見方もあるだろう。しかし3名は、「すでに手応えはある」と自信を見せる。2022年ローンチの『CADDi Drawer』、そしてそこから新アプリケーションとして2024年にリリースした『CADDi Quote』が順調にARRを伸ばしており、着実に構想の実現に向け進んでいるからだ。

取材内容等を基にFastGrowにて作成
小橋産業を大きく変えるため、製造業のあらゆるデータを扱うのが我々のプラットフォーム構想です。図面や受発注実績、加工ログなどをまず網羅するわけですが、そうした一般的に言われる“データ”以外も捉える必要があると考えています。みなさん、頭の中にあってデジタル化されていない“脳内データ”がありますよね。いわゆる知識や経験のことです。ここまで踏み込むことが不可欠なんです。ただし、脳をスキャンして得られるわけではありませんから、私たちはソフトウェアを通じてそれを引き出すことに挑戦しています。
具体的には、ベテランの方が実際に業務で判断する際のプロセスを細かく分析し、その判断に影響を与えている要素──例えば形状の特徴、素材の性質、加工の難易度など──を洗い出します。それらの要素がどのように組み合わさって最終的な判断につながっているのか、逆推論するかたちで、形式知化していきます。
これにより製造業の現場で既に、若手でもベテランと遜色のない意思決定や判断ができるようになり始めています。AIの力も借りながら、我々が『CADDi Manufacturing』で培ってきた業界の高い解像度を発揮することでこういった価値提供が可能になってきました。

祖業「CADDi Manufucturing」で培った知見をAIデータプラットフォームに統合(エンジニア向け会社紹介資料から転載)
小橋こうして、製造業の“人に依存する知識”を“組織知”として資産化しようとしています。とはいえ、その効果を実感するまで、さすがにかなりのロングスパンになります。「10年先の価値創出」はもちろん大事なのですが、「目の前の利益創出や効率化」も、それぞれの会社を経営していかなければならない以上、重要です。
『CADDi Drawer』や『CADDi Quote』は、「10年先」と「目の前」の利益創出の両立=”ダブルループ”を実現するんです。長期・短期の両方で、お客様の現場も、産業全体も、私たちも、みなハッピーになる構想です。
今回の事業統合は、Manufacturing事業で培った製造業の現場知識や理解といったキャディならではの強みを最大限に活かし、より大きく早く、産業にインパクトを生み出すための決断でした。まさに今、エンジニアリングチェーンからサプライチェーンまでを一気通貫で変革できる手応えを感じています。
桑名『CADDi Drawer』はいわゆるSaaSのようなプロダクト構造であり、製造フローの推進に欠かせない“図面”などのデータを扱うものなので、それぞれのお客様の日常業務の基盤として組み込まれています。『CADDi Manufacturing』よりもさらに深く入り込むサービス構造になっていることから、エンジニアとしても一つひとつの開発がお客様一人ひとりの行動変化につながる実感を得やすいことはやりがいにもつながっています。
また、以前の取材でCHRO幸松氏は「以前は『データ活用?ピンと来ない』と話していたあるお客様が、『CADDi Drawer』を導入した後に『あのシステムでこのデータをつないだら、こんなことができないかな?』と相談してくれるようになった」というエピソードを紹介してくれた。
このように、製造業というレガシーな産業において「データを活用する」という新たな“カルチャー”まで生み出しているのだ。『CADDi Drawer』は、製造業の現場にとってもそれだけインパクトの大きな新プロダクトなのである。

『CADDi Drawer』のプロダクト提供価値。製造業顧客のカルチャーを変革することまでを提供価値としている(提供:キャディ株式会社)
開発組織だって「ムーンショット」。
ハイグロースだからこそ得られる成長環境
ここまで見てきたとおり、開発組織のメンバーも一丸となり「壮大なミッションを実現する急成長プロダクト」を同時に複数、超高速で開発し続けていることが理解できたはずだ。前回の記事でキーワードとなった、異次元とも言える高い目標設定をするカルチャー「ムーンショット」について、開発組織にも浸透しているのだろうか?
藤倉断言しますが、開発組織においてもキャディの目標の高さは異常です(笑)。前職のSansanも成長スピードが凄まじく、もちろん高い目標を設定して新しいことに挑む文化はもちろん目覚ましいものでした。ただ、「ムーンショットな目標」という観点でいうと、キャディは輪を掛けて「無茶」な目標を掲げるカルチャーがある組織だと、ポジティブに感じています。
恐らくCEOの加藤のキャラクターが組織に反映されているのだと思いますが、みんな「さすがに無理じゃないですか?」という目標しか立てないんですよ。届きそうか届きそうでないかでいうと、そもそも全く届くイメージが持てない(笑)。でもそこから、「じゃあどうすれば届くのか?」という会話が社内のあらゆるシーンで行われているんですよね。
小橋これは「やり方が想像できることなら、誰かがすでにやっている」という考えがベースにあるのかなと思っています。

小橋我々は、何かの真似をしたいわけじゃない。今まで100年以上もの間、誰も実現できなかった「製造業の変革」を成し遂げようとしている。だから、他から学べるようなことをしていては到底実現できない。自分たちの頭で考えて、とてつもなく高いレベルでこれまでと違うことをしないといけない。そういう前提に立っているんだと思います。
桑名「ムーンショット」な目標を全員一丸となって追いかけていると、自分のポテンシャルも解放されていく実感があります。僕が最も自身の成長を感じるのは、ムーンショットな目標を達成するために「リーダーシップをとるとき」です。自分のスタンスを明確に打ち出しつつチームの合意を形成していく、そんな難しい挑戦を妥協せずにし続けないと、目標に届かないんです。
キャディの経営陣は常に、そういうスタンスを示してくれています。その背中を見てきたので、「自分もやらなければ!」と思えましたし、少しずつではありますが、高い目標を達成に導くリーダーシップが身についてきたと思います。

経営陣やビジネスサイド同様、“事業に熱い”開発組織
しかし、である。製造業という巨大かつ歴史や慣習もある世界においては、技術力や、異常なほど高い目標設定だけで産業変革を実現できるプロダクトを生み出せるわけではない。大切なのは“モノづくり”や“事業”への強いコミットメントだ。何のために開発し、ユーザーにどんなインパクトをもたらしたいのかという明確な想いである。小橋氏ら3名も、その点を繰り返し強調する。
小橋「良い“モノづくり”がしたい」というピュアな想いを持つことが、キャディの強い開発組織のコアになっています。技術力ももちろん大切ですが、その前に“想い”が大切だと考えているんです。
製造業には100年以上もの長い歴史があり、多くの現場では慣習や固定観念が残っています。そこに変化をもたらすには、技術面のみならず“この世界をより良く変えたい”という強い意志を共有していることが決定的に重要なんです。
そう語る小橋氏自身、CTOでありながら、「リソースの2割ほどを事業企画に、さらに2割ほどを営業に充てている」。顧客にプロダクトの価値を伝えるセールス現場にCTO自ら赴き、未来のプロダクト開発のための顧客インサイトを獲得したり、プロダクト価値の言語化に磨きをかけたりといった活動にもコミットしているというわけだ。
キャディに5年間在籍している桑名氏も、「今はこれまで以上に、エンジニアメンバーも事業成長に貢献できる、していこう、というモチベーションになっている」と語る。
桑名『CADDi Manufacturing』事業で私は、倉庫管理システムの開発を担うなど、サプライチェーン上の出荷フローにおける生産性の向上・効率化に貢献してきました。しかし場合によっては、そもそも顧客側のコストとして圧倒的な負担となっていたのは、人件費ではなく海外から来る部品の輸送費だった、ということも少なからずあったんです。それって、もはや我々の力ではどうすることもできない……。といった難しさを感じるときも、当時はありました。
一方、『CADDi Drawer』は製造業(サプライチェーンやエンジニアリングチェーン)の上流から下流まで、エンジニアリングやテクノロジー活用で、顧客の直接的な価値や利益に貢献できます。つまり、エンジニアが事業に対して影響を与えられるレバー(事業成長に影響を及ぼすことができる変数)が、『CADDi Manufacturing』時代よりも、圧倒的に増えているんです。事実、セールスメンバーからは「プロダクト開発が進めば進むほど顧客に導入してもらいやすくなる」といった声が聞こえてきますし、開発組織に対する社内の期待感は、他部門も含めて高まっているなと感じています。
藤倉キャディでなければ生みだせなかった機能だろうな、と話を聞いて驚いたことがありました。AI技術を用いた「類似図面検索」という機能です。
ある図面をベースに、それに類似した図面を瞬時に検索することができる、という機能なのですが、そもそも何をもって“類似”を判断するべきかという、プロダクトの核になる部分を決めるため、開発メンバーらは社内にいる製造業出身メンバーに聞いて回ったそうです。実際の図面を見せて「この図面とこの図面は似ていますか?」という具合に、何度も何度も。こうした泥臭いアプローチも厭わずに注力できることはキャディのテックメンバーの強みだと思います。
仮に、全くのゼロから類似図面検索のソフトウェアを作ろうと思ったら、どこから手を着けていいかわからず、技術の使い方が複雑になってしまうでしょう。でも、キャディには先のManufacturing事業で培った図面データが既にたくさんありましたし、製造業の知見を持つ多くのエキスパートがいて、血の滲むような努力を積み重ねながらソフトウェアを開発してきた経験がありました。だからこそ、「核となる判断基準を、どのようなアプローチで探るべきか」の勘所を開発陣もすぐに見つけることができた。これは事業成長や顧客貢献へのコミットがあり、そのために社内メンバーの知見をフル活用しようとする開発組織でなければ、実現できないことです。
「事業価値が高まるなら、開発だけでなくなんでもやる」というコミットがこの3名の発言から汲み取れる。これがキャディの開発組織の強みであり、急成長スタートアップの元CTOや元テックリードの精鋭たちも、まさにこの「事業への熱い想い」に共感してキャディにジョインしている。
本連載1記事目で詳細にお伝えしたように、藤倉氏だけでなく、ユーザベースでCTOを務めた杉浦正明氏や、delyでCTOを務めた井上崇嗣氏など、3名もの元CTOが直近1年で集まった。他にも、スタートアップでテックリードを務めたり、Kaggleというデータ分析コンペティションの最高峰の称号であるGrandmasterの保持者が2人も在籍しているほどである。

開発組織の主要メンバー。著名企業で活躍してきたスペシャリストが集う(提供:キャディ株式会社)
繰り返しであるが、これだけ実績のある彼らをキャディへと惹きつけるものは「壮大なミッション」である。そのミッションへの強烈な共感こそが、桑名氏や藤倉氏をキャディの第二章に進ませたのだ。
桑名ずっと『CADDi Manufacturing』の開発に心血を注いできた立場として、最初に発表を聞いたときには驚きと悔しさを覚えました。入社した当時はそれがメインの事業でしたし、そこに共感して入った部分もあったので。
でも同時に、僕たちの「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」というミッションを「もっと早く成し遂げなければ……」という思いもありました。そう考えると、たしかに『CADDi Drawer』にフォーカスしたほうが良いのかもしれない。素直にそう感じ、経営陣の意思決定に納得する自分がいました。
私が率いるエンジニアチームでも、この事業統合を新たなチャンスと捉え、より強度の高い業務進行をするようになっています。捉えにくかった変数もしっかりとKPIにつながるよう数値化しつつ、アウトプットではなくアウトカム(お客様に提供できた価値)で評価や振り返りをする部分を増やしています。
キャディの開発陣は、多彩な専門分野のスペシャリストで構成されています。たとえば、先に挙げた検索の仕組みもそうですし、機械学習の仕組みもそうです。いろいろなベクトルで強みが発揮され、プラットフォーム構想の開発を力強く支える要素を担っていると感じますね。
藤倉私も『CADDi Manufacturing』があってこそのキャディの強さを感じて入社を決めた部分はあったので、正直、事業統合の意思決定にはかなり驚きました。ですが、桑名さんと同じように納得感は大きかったので、もともと想定していた「VPoEとして最高の開発組織づくりを牽引する」という私自身の使命を変わらず遂行していくだけだ、と気持ちをすぐに切り替えました。
目指す壮大なミッションには変わりはありませんし、「何をどうつくるか」を任せられる、開発チームの強いエンジニアたちもいます。私は私の強みを活かし、組織づくりにフォーカスしていきたいと思っています。
「3年で数十個」のプロダクト開発…世界最大産業の変革を担うからこその圧倒的な開発スピード
キャディの開発組織を支える根幹には、高い技術力や秀逸なプロダクトだけでなく、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」というミッションに対する、非常に強い共感とコミット、そしてムーンショットな目標達成を志向するカルチャーがあった。そしてそれゆえに、事業統合という変革期を経て、「誰も成し遂げたことのない100年以上変わらない製造業の変革」という大きな目標達成のためにより一丸となり、ハイスピードな製造業AIデータプラットフォームの開発が進んでいるようだ。
桑名今、『CADDi Drawer』はそのコアの価値が確立され、手前味噌ですが凄まじい勢いで業界に浸透し始めているフェーズです。これからは、どうやってさらなる付加価値をつくり、顧客課題をより深く解決できるプロダクト群を創り上げていくかが重要になります。その手段が、100以上の開発アイデアであり、そのために妥協せず取り組む一人ひとりの仕事ぶりになるでしょう。
これからいくつものチームが並行して、プラットフォームに魅力的な機能を次々に追加していきます。100年以上解決されていない製造業の課題に挑むプロダクト開発にこのスピード感で関われることは、エンジニアにとってチャレンジングな環境ですし、これまで以上に事業も自分自身の成長も、加速していく予感がありますね。
小橋たしかに実現までの道のりは相当タフなものになるでしょう。けれども、僕らが社会に出せる価値、インパクトのアップサイドが極めて大きいということを考えると、興奮してきませんか?製造業はいまだに日本のGDPの2割前後を占めているわけですし、グローバルで見ても世界最大の産業です。生み出せるインパクトが凄まじく大きいので、無限に青天井の挑戦ができる。これはすごくワクワクしますよね。
藤倉そうですよね。たかだか600人で「世界中の製造業のあり方を変えましょう」なんて言ったら、足りないに決まってます(笑)。
今の製造業の在り姿は、長い歴史の中で皆が“頑張って”進化を重ねてきた結果ですよね。決して誰かがサボっていたわけではないし、悪くしてやろうと思っていたわけでもない。それでもこれだけの課題が残っている。ということは、これは構造的な問題。製造業の新しい可能性を引き出そうと思ったら、構造を変えない限り進化がないように思えます。
でも、「構造を変える」と口で言うのは簡単ですが、グローバルで数千兆円規模の製造業の市場構造を再編するのは決して容易ではありません。短期の下流課題から長期の上流課題まで、あらゆる工程を抜本的に変えていく必要がある。しかし、それを実現できれば製造業全体に非常に大きなインパクトがもたらされるはずです。そこでキャディが掲げるのが、「製造業AIデータプラットフォーム」構想であり、今後3年で数十個のプロダクトを高速で立ち上げていく計画ということです。
これから、『CADDi Drawer』のグロースもあれば、全く新しいアプリケーションをゼロから構築する機会もたくさんあります。どれも非常に高いハードルを設定しつつも超高速で実現に向けて突き進む「ムーンショット」なカルチャーの中で進められるため、「グローバル製造業の変革」という壮大なミッションにコミットできる方であれば、必ず大きな成長を実感できる環境であると思います。

最後に、本連載で紐解いていた3つの謎についての実態を整理しておくことにする。
謎1:事業は伸びているのか?
→実態:第二創業期を迎え、むしろよりハイグロースに
謎2:組織はもう出来上がっている?
→実態:600人でもまだ0.1合目。チャンスやポジションは増え続けている
謎3:“成果がすべて”なドライなカルチャー?
→実態:壮大なミッションに挑む、“冷静で熱い”集団
本連載1記事目の末尾で、「この連載を読めば、新たなるキャディの姿がくっきりと見え、“これぞ急成長スタートアップ”と刺激を受けること間違いないのではないか」と記した。
あなたはどのように感じたであろうか?
- 「第二章とカッコよく言っているが、事業統合ということは成長率が鈍化しているのでは・・・?」
- 「日本だけで見ても超巨大産業である製造業を、スタートアップ起点で変革するのは不可能じゃないか?」
- 「グローバル拠点も増えていると言っているが、実績とか評判を耳にすることもないし・・・」
正直に言えば、FastGrow編集部も取材前にはこのような印象を少なからず抱いていた。
しかし今ならFastGrowは自信をもって断言できる。
- 「今のキャディは、世界中のスタートアップパーソンが驚愕するようなハイペースでグロースしている、異次元なスタートアップである」
- 「近い将来、日本のスタートアップと言えばキャディだろ?と世界中から聞こえてくる日がきっとくる」
ということを。
是非、ここまで読み進めていただいた読者には、自身で一度、キャディの経営陣やメンバーに触れ、その熱量や実態を確かめてみてもらいたい。
採用拡大中、情報はこちらから
エンジニア向け採用情報はこちらから
こちらの記事は2024年12月27日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。