成長していく経営人材、たった1つの共通項は「コミットメント」──「ギリギリ大きな球」を投げ、失敗から学び切る育成設計
ラクスル株式会社(以下、ラクスル)グループCRO田部氏に「経営人材の育成・輩出」について聞く本連載。2記事目として「コミットメント/オーナーシップ」という、スタートアップパーソンなら聞いたことがあるはずのマインドセットについて深掘りしていく。
企業においてはどうしても「若手は」「ベテランは」「社長は」といった、わかりやすいレッテルによって、その働き方やマインドセットについての意見が飛び交う。こうした議論を俯瞰的に観察し、自身の立ち位置や目指す姿をメタ認知することが、成長には不可欠な要素となる。
とくに「社長はなぜ、土日でもSlackで連絡してくるのか?」という点について、深く考えてみたことはあるだろうか?田部氏は、こうした問いにこそ本質が眠っていると考える(土日の勤務を肯定する意味では、もちろんない)。自身の成長につながる新たなきっかけが、この記事でも間違いなく得られるだろう。
「最後の砦」である意識、それがコミットメント
育成の過程で、うまくいく人と、つまずいてしまう人にはどのようなパターンの違いがありますか?
田部違いは突き詰めると一つですね。コミットメントです。
この点に、年齢や経験は、本来はあまり関係ありません。自分が関わっていることに対して、最後まで責任を持つ「最後の砦」であるという意識を持って取り組み続けていけるかどうかが全てです。
それでも「残業はできるだけせずに成果を出したい」と、効率をまず追い求める若手が多い、という不満の声も聞かれます。こうした点は気になりませんか?
田部それで成果を残せるのならいいわけですが、「自分ゴトとして考え切れていないだろうな」と感じさせてしまうような姿勢に見えたら、こちらも不安にはなりますよね(笑)。
たとえば、たまに「土日に社長から連絡が来た、パワハラだ」と訴えられる場面を見聞きします。おっしゃることはわかります。労働基準法や社会通念に照らして、良いことではありません。ですが「社長とはそういう生き物だ」という考え方も必要です。
社長にもなれば「土日なんて関係ない」と言ってずっと仕事をしている人も多くいますよね。これは「仕事がすべて自分ゴトであり、成果が出続けるように何でもやる」という意識から、自然に起きる行動なわけです。たとえばこういう姿勢に、「コミットメントの強さ」がにじみ出ます。
社長や経営層ではなくても、土日の時間に、ちょっと意識を変えることならできるはずというような指摘でしょうか。
田部そうですね、「土日でも仕事のことを考えずにはいられない、アイデアが次から次へと出てきて、早く事業で試したい」というようなのが、強いコミットメントのある状態だと言えるのではないでしょうか。オーナーシップがある状態とも表現できます。
失敗に自ら向き合うことで芽生えるオーナーシップ
そうしたコミットメントやオーナーシップは、どのように育まれていくと考えていますか?
田部自らの責任で失敗し、それを乗り越えようとすることで、育まれていきます。
言葉で話して「オーナーシップを持とう」などといくら伝えても、それだけでは、人の在り方や心の持ちようはなかなか変わりません。必要なのは「心の底から納得し、挽回しようとする気持ち」なんです。
たとえばアメリカのプロ野球では、コーチは選手から「教えてほしい」と言われるまで教えないという話を聞いたことがあります。それと同じで、自ら課題に気づき、変わりたいと願わない限り、本当の意味での成長にはつながりません。目の前の行動を一つ変えて終わりになってしまい、それっきりです。
そうではなく、失敗につながるような意思決定を自ら担うことで、課題を深く認識し、様々な観点から変わろうとするきっかけを得ることが必要です。育成する側がいくら仕組みを整えても、当の本人が「自分の責任で失敗したから、自分が変わることで挽回していこう」という気持ちを持てていないと意味はありません。とにかくこの気持ちを抱くようになってもらいたいですね。
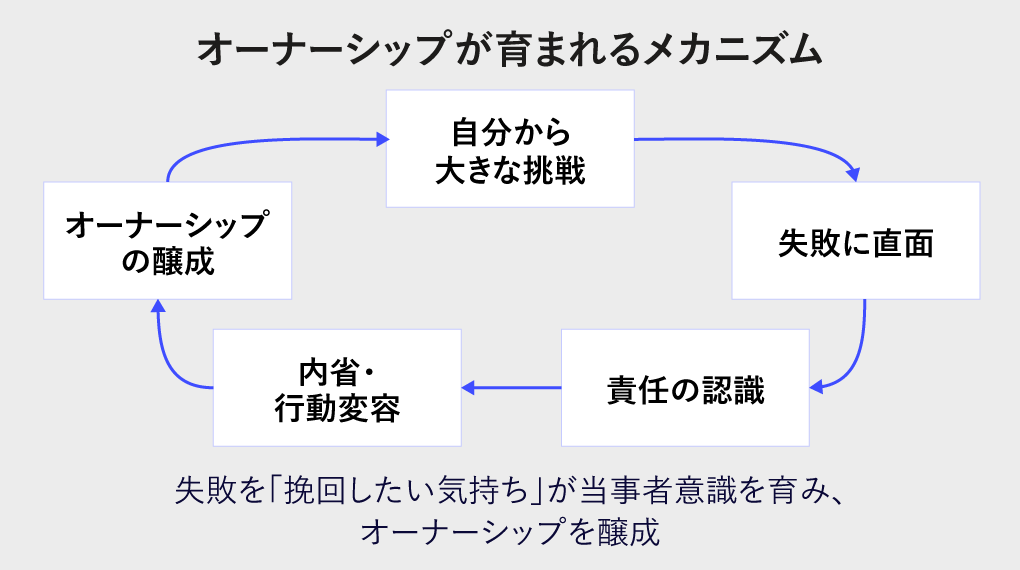
取材内容等を基にFastGrowにて作成
そうした強いコミットメントを持っている状態は、外から見てもわかるものですか?
田部本当に強いコミットメントやオーナーシップを持っていれば、「自分の言葉」でしっかり語れるはずなので、わかります。新卒でも中途でも、採用面接で私はこの点しか見ていないくらいです。
能力の有無だけなら、誰でも口先で語れます。ですが、その能力がどのような失敗と成功における学びとして身に着いたのかという点こそが重要。自分ゴトとして挑戦してきた経験があるのなら、ちゃんと言語化できるはずだと思うんです。
「ギリギリ大きな球」を、経営陣や上長が投げる責任
とはいえ、ラクスルとして育成の仕組みはかなり意識的につくり込んできていますよね。
田部はい、若手には大きな挑戦をさせて、その中で起きる失敗を許容できる状態でいる、ということを何よりも重要だと考え、設計しています。もちろん、会社が潰れるような失敗はさせられませんが、その手前の、ギリギリの大きさの球を渡し、失敗から学べるようにしているんです。
そして、失敗から学ぶために重要なのは、「目指す姿(理想)と現状のギャップ」を明確にすること。このことをスピーディーに進めるためには、上長を中心としたまわりのメンバーの貢献も不可欠だと考えています。
たとえば上長が1on1などで単に「この仕事はダメだった」とフィードバックするだけでは進まないのです。それだけだと、業務上の指摘に過ぎず、新たな能力開発にまでつながっていきません。
必要なのは、「目指すべき姿はこうだったよね。君がやったことはこうだった。この差分は何だろう?」と一緒に考えることです。差分を本人が常に意識するようになれば、成長への渇望感が生まれ、新たなアクションをせずにはいられないはず。
とはいえ、これを自分一人でやるのは難しいので、上長や会社がその環境を整え、課題認識を引き出してあげることも必要です。

取材内容等を基にFastGrowにて作成
「目指す姿」はどのように考えるべきなのでしょうか。
田部上長から提示することもあれば、本人が自ら設定することもあるでしょう。状況に応じて理想も変わり得るはずですから、社内にも社外にも、意識すべきロールモデルを置けるといいと思います。
ラクスルのように、新卒入社が毎年ある企業では、一足先に次のステップに進んでいる先輩が身近にいるはずです。まずはそうした存在を常に意識し、できるだけ会話をして新たな気付きを増やすようにできるといいですね。
そのうち、だんだんとロールモデルを探すのが難しくなるのですが、そういう存在は社外に求めてもいいわけです。私も、経営しているノバセルで社外取締役を足立光さん(ファミリーマートCMO)にお願いすることで、ロールモデルとして身近に感じつつ、厳しいフィードバックも日々いただくようにしています。
ラクスル創業者の松本恭攝(ジョーシスCEO)とも「経営者になっても、自分にはないものを持っている人たちと話して課題認識を持つようにすることで、伸び続けられる」という話をしています。だから、松本も私も自分自身で意識しつつ、仕組みもつくろうとしているんです。
ラクスルでは引き続き、若手経営人材の候補を大募集中(採用情報はこちらから)
「若手経営人材」の採用・育成についてお悩みなら
こちらの記事は2025年11月07日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
次の記事
連載ラクスル流「若手経営人材」になるための条件——若手から経営へ至る“レバー”の増やし方
3記事 | 最終更新 2025.11.10おすすめの関連記事
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.21:AstroX株式会社 大谷和彦氏
- AstroX株式会社 Director, Business Development
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.20:コミューン 宮川 知也氏
- コミューン株式会社 VP of CS
世のマーケターに告ぐ。「我々の責務は事業を伸ばすこと。広告に非ず」──スタートアップのグロースを牽引するマーケティングの立役者4名が語る
- 株式会社GrowthCamp 共同代表
「経験や年次は関係ない」──事業家輩出企業のUPSIDER×ノバセルに訊く、リーダー・意思決定者を育むスタートアップの共通項
- 株式会社UPSIDER 代表取締役
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.23:ファインディ株式会社 山田 郷氏
- ファインディ株式会社 執行役員 プラットフォーム事業・Findy Tools事業担当
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.22:J-CAT株式会社 牧野雄作氏
- J-CAT株式会社 執行役員/President
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社ネクスタ 豊田優雅氏
- 株式会社ネクスタ 営業部 SFAセールグループ
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社Hajimari 亀田壮司氏
- 株式会社Hajimari ITプロパートナーズ事業部・ゼネラルマネージャー(GM)



