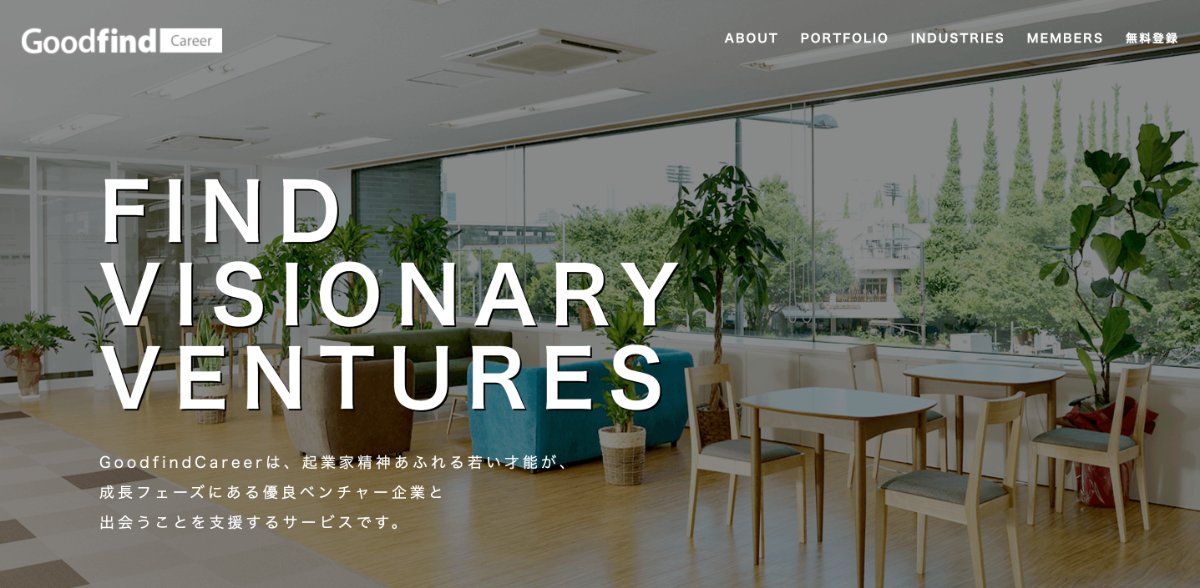成長のために「日常」と別れよう──天才はあきらめた
ようこそ狂気とカオスの世界へ!
6月もはじまり、緊急事態宣言も明けた今日この頃。読者の皆様はいかがお過ごしだろうか。
「新しい日常」もはじまった、スタートダッシュを切ろうじゃないか。そこで本日のテーマは「どうすれば成長できるか」だ。
日常を続けていても、人は変わらない
さて、オチからお話しよう。人の成長を決める要素の割合は決まっている。直接的な経験が7割。他者の観察やアドバイスが2割。勉強(読書や研修)が1割だ。
「おいおい、結局経験かよ。長く働けってことかよ」
確かに、私もそう思っていた。ただ、どうやら違うらしい。
突然だが話は変わって、ジムで体を動かすこともできなかったので、5月からオンラインのトレーニング講座に通っている。
そこで、先生に「トレーニングと運動との違いがわかりますか?」と言われた。「いくら運動をしていても、体に変化は起こらないので、トレーニングをしましょう」と。
自粛中に"自称トレーニング"に勤しんでいた私は、「まあ自分はトレーニングしてるし」と高をくくって話を聞いていた。
さて、トレーニングの原則とは、
- Overload:過負荷、キツいことをしないといけない
- Form Strict:きちんと正しい方法で
- All Out:全部出し切ること
だそうだ。
そして、その日に気付かされたことは、私がずっと続けていたのは"トレーニング"ではなく"運動"だった、ということだ。オンラインの講座が終わった瞬間、見事に自宅で横になって動けなくなった。しかも実際に動いたのは60分未満。
どれだけ長く動いていても、上記が満たされていなければ、それは運動であって、トレーニングではない。これは、仕事だって同じだ。出来ることだけやっていても、負荷が足りない。負荷が高くても、自己流のやり方だけだとうまくならない。そして、ちゃんと全部出し切ること。
日常の内側に居続けても、あなたは何も変わらない。仕事でもトレーニングすることだ。かふか、ふぉーむすてゅりくと、おーるあうと、……呪文のように唱えよう。
リフレクションのススメ
ただ、経験だけしていれば人は成長できるのか、というとそうではない。同じ経験をしているはずなのに、成長する人としない人とに分かれるのは、なぜだろうか。
それは内省(リフレクション)能力の違いだ。内省力が高い人は、「経験する→内省する→教訓を引き出す→新しい状況へ適用する」というサイクルが回っている。
例えば、メールでの誤字脱字という定番のミスをしたとしよう。内省力が低い人は「すみませんでした!」と言って、それでおしまい。そしてまた誤字脱字を繰り返す。
一方で、内省力が高い人は、「なぜ誤字脱字をしたのか」「どうすれば誤字脱字をしないのか」を考える(内省)。そして、そこから学び(教訓)を得て、仕組み(他の状況への適用)をつくる。
- 個人名やサービス名はコピペする(絶対に手入力しない)
- メールをダブルチェックする、ダブルチェックツールをその場でインストールする
- 文章を音読する
そして、この3つを次回のメール送信から運用できるようにチェックリストをつくってデスクトップに貼る。
今日、怒られたり、フィードバックされた事象から、なんの教訓も仕組みも生まれていなければ、それは危機感を覚えた方がいい。
さらに賢者は他人の経験からも学ぶ。同期や先輩の成功や失敗からも、同じように内省できる人は、それだけ成長の打席に立てる。だから同期でも成長のスピードが違うのだ。
先輩から教わったおすすめの内省方法があるので紹介しよう。一日の終わりに、紙とペンを用意する。そして、紙の真ん中に横線を引く。そして、上部の中心に縦線を入れる。これで準備完了。
左上には、今日起こったことを書く(事実ベース、客観的な出来事)。右上には感じたこと、気づきを書く(主観的な感情、学び)。そして、下部には明日から取り組むこと(新しくはじめること、これまでやっていたが止めること、改善すること)を書く。これで1日を振り返るフォーマットとシステムが出来上がる。
慣れれば5-10分くらいでできる。ちょうど「ほぼ日手帳」がそのようなデザインになっているので、私は長らく手帳でこの振り返りを続けている。日報があるなら、日報を書く前にこの内省ワークをやってから日報を書くのもいい。
天才でないなら努力するしかない
「なんだ勉強は1割程度なのか。じゃあ、そんなに意味がないな」。まあまあ、そんなに慌てないで。
たかが1割、されど1割だ。人の3倍経験するのはほぼ不可能だ。1日は24時間しかない。しかも先輩に経験で勝るには、分が悪い。だからこその勉強だ。勉強だけが唯一、時間を圧縮できるし、人の3倍努力できる。
あなたが配属された部署で必要とされる専門知識があるはずだ。意外なことに、驚くほどに人は勉強しない。だからこれはチャンスだ。
書店で(Amazonでも)、その専門コーナーに行って、20冊。とにかく買い漁って、読み進めていくことだ。
1週間で1冊。1ヶ月で4冊。5ヶ月後の10月の終わりには、あなたは知識だけなら、部署で上位5%には入れるはずだ。なんなら一番になっているかもしれない。
もちろん、全てができるようにはなっていないだろう。ただ、「できない」だけで、とりあえず「知らない」ということはない。
あなたが知らないということは、他の人もほぼ知らない。こんな安心感はない。それは自信にもつながる。勉強に才能はいらない。ただ努力すればいい。誰でもできる方法だ。
ちなみに、とあるベンチャーのCFOが見習いだったころ、師匠に言われた最初の課題は、「参考図書を20冊教えるから、2ヶ月後に全て読んで、感想出してごらん」だったらしい。
赤いメガネの芸人が言っていた。天才とは、何者かになるための労力を、呼吸でもするようにできる人だと。ただ、天才でない人間は地獄のように努力するしかないのだと。
努力する理由はなんだっていい。「モテたい」「見返したい」「認められたい」。大事なことは、自分を努力するように仕向けることだ。
何者かになりたいと無為に嘆くよりも、目の前の努力に情熱を注ぎ込んだ方がいい。天才になれなかったのなら、単に努力すればいい。
これを読んでいるあなたは天才じゃないかもしれない。そんな私も、たりない私だ。ただ、日々「日常」から出ることに努め、努力を積み重ねていけば、成長することはできる。そんな新しい日常を愛でようじゃないか。
連載第6回目は、6月19日公開
「プラトーがやってきた──好きになる努力と工夫を」 乞うご期待!
ベンチャーでの市場価値が知りたい、大手エージェントでは紹介されない優良ベンチャーが知りたい方はこちら
こちらの記事は2020年06月05日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
次の記事
連載ベンチャー新卒1年目の教科書
10記事 | 最終更新 2020.08.14おすすめの関連記事
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.21:AstroX株式会社 大谷和彦氏
- AstroX株式会社 Director, Business Development
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.20:コミューン 宮川 知也氏
- コミューン株式会社 VP of CS
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.23:ファインディ株式会社 山田 郷氏
- ファインディ株式会社 執行役員 プラットフォーム事業・Findy Tools事業担当
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.22:J-CAT株式会社 牧野雄作氏
- J-CAT株式会社 執行役員/President
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社ネクスタ 豊田優雅氏
- 株式会社ネクスタ 営業部 SFAセールグループ
【ベンチャーキーパーソン名鑑】PdM(プロダクトマネージャー)編 Vol.12:株式会社タックスナップ 金丸翔氏
- 株式会社タックスナップ CTO
【ベンチャーキーパーソン名鑑】BizDev編 Vol.25:株式会社Hajimari 亀田壮司氏
- 株式会社Hajimari ITプロパートナーズ事業部・ゼネラルマネージャー(GM)
【ベンチャーキーパーソン名鑑】CTO編Vol.1:ミクステンド株式会社 ラジェッシュ・ジャヤン氏
- ミクステンド株式会社 CTO